(東京都墨田区) |
 ここにも横綱力士碑があることを不覚にもすっかり忘れていた筆者。
同行者と3人でふらりふらりと宿禰神社さして歩いたのは良かったが、どうやら行き過ぎたらしい。引っ返して仲通りを歩いてどうやらこうやら見つけたが…案外小さいなこりゃ。
横綱碑そのものよりも、小ぢんまりしたその狭い空間に驚いてしまった我々。実は大きな通りに面しているのもかかわらず、おまけに持ってた地図と位置が少し違う…。
さてここに祀られている野見宿禰、垂仁天皇7年の7月7日、天覧のもとで當麻蹴速と力比べ、宿禰は蹴速のあばら骨を蹴折って勝ち、これにより今や日本相撲の始祖として、崇め奉られてきた人物である。
尤も、神話伝説の域は出ないのだが。 ここにも横綱力士碑があることを不覚にもすっかり忘れていた筆者。
同行者と3人でふらりふらりと宿禰神社さして歩いたのは良かったが、どうやら行き過ぎたらしい。引っ返して仲通りを歩いてどうやらこうやら見つけたが…案外小さいなこりゃ。
横綱碑そのものよりも、小ぢんまりしたその狭い空間に驚いてしまった我々。実は大きな通りに面しているのもかかわらず、おまけに持ってた地図と位置が少し違う…。
さてここに祀られている野見宿禰、垂仁天皇7年の7月7日、天覧のもとで當麻蹴速と力比べ、宿禰は蹴速のあばら骨を蹴折って勝ち、これにより今や日本相撲の始祖として、崇め奉られてきた人物である。
尤も、神話伝説の域は出ないのだが。
 さて、横綱碑は、鳥居の左側に2基ある。一方は朝汐まで、もう一方は柏戸以降。古い方の石には昭和二十七年十一月之建とある。
生存している横綱は赤字になっている。玉の海の赤はずいぶん慌しく消された様子が窺えるが、柏戸が赤いままだった。
曙の赤が消えかかっているというのに…。他には大して何もないところである。新横綱はここで土俵入りを奉納するわけだが、それにしても狭い。
日本における相撲の祖という宿禰さまを崇めるのだから土俵入りをやるくらい当然ではあるが、大の力士3人が蹲踞するだけでも窮屈そうな気がした。
さて、横綱碑は、鳥居の左側に2基ある。一方は朝汐まで、もう一方は柏戸以降。古い方の石には昭和二十七年十一月之建とある。
生存している横綱は赤字になっている。玉の海の赤はずいぶん慌しく消された様子が窺えるが、柏戸が赤いままだった。
曙の赤が消えかかっているというのに…。他には大して何もないところである。新横綱はここで土俵入りを奉納するわけだが、それにしても狭い。
日本における相撲の祖という宿禰さまを崇めるのだから土俵入りをやるくらい当然ではあるが、大の力士3人が蹲踞するだけでも窮屈そうな気がした。 |
||||
以上 平成9年7月27日訪問分 |
||||
| 15年ぶりにやってきた。相変わらず小さな社で、横綱碑には白鵬まで刻まれている。過ぎたる日子を思わせるのは、朝汐までのほうである。
鏡里逝き、若乃花も歿し、とうとう平成22年をもって存命者がなくなった。この横綱碑、代数・生国・四股名の順で刻んであるが、
仔細にみると、生国の記載が変わってきている。佐田の山までは旧国名によっているが、玉の海になって突然「愛知県」となり、
隆の里が「青森」で双羽黒は「三重県」、かと思えば旭富士はまた「青森」で、貴乃花と若乃花は「東京」と、まとまりがない。
彫ったものを今さらどうにもできはしないし、頼みます鑿の宿禰さまとか薄ら寒いことを考えながら、前回全く書かなかった由来記をちょっとだけ。 ここはかつて、関脇浪ノ音の11代振分が管理していた。大正12年から、定年制施行後青森に移るまでというから、およそ40年に及ぶ。 神社の起こりについて昭和31年に振分本人の語ったところによれば(小島貞二編「はなしの土俵」)、「当時五条公爵家に宿禰神社があったのを篤信家の初代高砂が、 部屋でお祭りしたいと申し出て、ときの総理大臣・黒田清隆の口添えで実現したものだと聞いております」「この土地は津軽の藩主の中屋敷だったのを払い下げて頂き、 鬼門に当たるこの場所へご遷座したのが明治十七年でしたか、朝野の名士が集まって大変なものだったと聞いてますよ」と。 これが関東大震災で焼けて仮社殿となった頃からが、振分管理の時代である。さらに昭和20年3月の東京大空襲に遭って焼失、 27年から再建が始まって28年6月7日に完成したのが現在の姿ということになるのだ。東京場所初日前々日には、いつも神事が執り行われる。 社殿を戍る狛犬が、横綱碑をも打ちまもる。そこに日馬富士の名が刻まれるのは、もうすぐだ。
|
||||
以上 平成24年9月22日訪問分 |
| (参考資料) | |
| ・ | 相撲史跡研究会(編)「相撲の史跡」1 |
| ・ | 小島貞二「はなしの土俵」(「相撲」連載)17 振分健蔵(昭和32年1月号) |
| ・ | 水野尚文「ご存じですか?知られざる両国名所"相撲の神様"を祀る野見宿禰神社」(「相撲」平成15年6月号) |
前画面に戻る 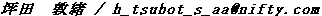 | |



