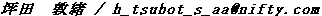| 1: | 花道から入場。呼出しが柝を入れながら先頭を歩み、行司、露払い、横綱、太刀持ちと続く。呼出しは赤房下または白房下にとどまってなおも柝を入れる。行司は東または西の溜まりに進み、二字口から土俵に上がる。東の場合は赤房下で太刀持ちと露払いの順序を入れ替える。① |
|
| 2: | 3力士、東または西の溜まりに進んで土俵に向く。場内放送が「横綱、●●」と述べたところで土俵に上がり、円の内側に沿って蹲踞。行司は二字口で一度立ち止まり、正面側の足から3歩半で土俵中央に進んで正面を向き、向正面に右足から1歩半後退して蹲踞。② |
|
 |  |
| 3: | 以下、特に断りがない場合は横綱力士の所作を示す。ここから塵浄水の所作。両腕を前下方に垂らして上体を前に倒し、拝礼をする(このとき行司も礼をしていたが、平成に入ってすぐの頃からは見かけない)。③ |
|
|
 |  |
|
|
 |  |
| 7: | 打った両掌を上向きに開く(やらなくても構わない)。⑥ |
|
| 8: | 両腕を水平かもう少し上ぐらいの高さになるように左右に広げる。④ |
|
 |  |
|
| 10: | 両腕を下ろし、立ち上がり、土俵中央に正面側の足から3歩半で進んで正面を向く。このとき行司は右足から3歩半で向正面に後退し、蹲踞する。⑦ |
|
 |  |
| 11: | 行司が「シーッ」と警蹕を発する。両腕を広げ、そして柏手を打つ。④ |
|
|
 |  |
|
| 14: | 打った両掌を上向きに開く(やらなくても構わない)。⑩ |
|
 |  |
| 15: | 左肘を曲げて左掌を胸から脇腹あたりにつけ、右腕を水平かもう少し上ぐらいの高さになるように真右に広げ、右掌を返す。⑪ |
|
|
 |  |
|
 | ここからのせり上がりは、いわゆる「雲龍型」と「不知火型」とで型が分かれる。左に雲龍型、右に不知火型を並べる。行司はここまでずっと軍配を水平にして捧げ持ち、左手で支えているが、横綱が四股を踏んだところで房を土俵に落とし、正面から見て反時計廻り→時計廻りの順に1回ずつ房を振り廻し、再度房紐をたたんで元のように軍配を捧げ持つ。 |
| 18~21: | 腰を割り、左肘を曲げて左掌を胸から脇腹あたりにつけ、右腕を右下方に下げる。すり足で前方ににじり寄りながら徐々に立ち上がり、同時に右腕を水平かもう少し上ぐらいの高さになるまで差し上げ、右掌を返す。⑧ |
| | 22~25: | 腰を割り、両腕を左右下方に下げる。すり足で前方ににじり寄りながら徐々に立ち上がり、同時に両腕を水平かもう少し上ぐらいの高さになるまで差し上げ、両掌を返す。⑬ |
|
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
| |
| 以降はいずれの型でも同様に行う。 |  |
|
| 28: | 登場した側と反対の足を軸にして登場した側の二字口の方を向くように体を廻し、3歩半で二字口に戻る。このとき行司は右足から3歩半で土俵中央寄りに進み出る。⑪ |
|
 |  |
| 29: | 正面に尻を向けないように体を廻し、蹲踞して塵浄水。3~9を繰り返す。⑭ |
|
| 30: | 呼出しは赤房下または白房下で柝を入れる。横綱は両腕を下ろし、3力士及び行司は立ち上がり、3力士は正面に尻を向けないように体を廻して土俵を下りる。西の場合は白房下で太刀持ちと露払いを入れ替える。行司は土俵中央に右足から1歩半で進み出て登場した側の二字口を向き、正面側の足から二字口に進んで土俵を下りる。露払い、横綱、太刀持ち、行司の順で花道を退場する(呼出しは柝を入れ終わるまで退場しない)。⑬ |
|
 |  |
| (参考文献) |
| 横綱土俵入りに限らず、横綱については、 |
| ・ | 新田一郎「相撲の歴史」講談社(講談社学術文庫)、平成22年(原書:山川出版社、平成6年) |
| 横綱土俵入りの「故実」とされる文章を載せるのは、 |
| ・ | 式守蝸牛「相撲隠雲解」寛政5年(影印:「VANVAN相撲界(昭和58年秋季号)」ベースボール・マガジン社、昭和58年) |
| 「雲龍型」「不知火型」の名称の件については、いくつかの記事があるが、まとまった記事のうち新しいものとして、 |
| ・ | 長山聡「序ノ口ゼミナール(13) 土俵入りに型が二つあるのは?」(「大相撲」平成19年9月号、読売新聞社所収) |
| これを取り上げたテレビ番組の一つとして、 |
| ・ | テレビ東京「追跡LIVE! SPORTS ウォッチャー」平成29年1月28日放送 |
| 一礼については、 |
| ・ | 三保ヶ関国秋「ちょいと一言・北の湖の土俵入りについて」(「相撲」昭和50年1月号、ベースボール・マガジン社所収) |
| 歴代横綱の土俵入り映像としては、17代横綱小錦から69代横綱白鵬までを集成した、 |
| ・ | 「特典映像 『歴代横綱土俵入り』」(「映像で見る国技大相撲 第20号」ベースボール・マガジン社所収、平成22年) |
|
| 本文中の丸数字に対応するのは、以下の通り。 |
| ① | 27年9月2日目の白鵬(太刀持ち魁聖・露払い旭秀鵬) |
| ② | 27年7月8日目の鶴竜(太刀持ち時天空・露払い青狼) |
| ③ | 27年11月2日目の日馬富士(太刀持ち誉富士・露払い宝富士) |
| ④ | 25年5月7日目の日馬富士(太刀持ち安美錦・露払い宝富士) |
| ⑤ | 25年5月6日目の日馬富士(太刀持ち安美錦・露払い宝富士) |
| ⑥ | 25年5月8日目の日馬富士(太刀持ち安美錦・露払い宝富士) |
| ⑦ | 29年11月初日の稀勢の里(太刀持ち松鳳山・露払い輝) |
| ⑧ | 29年11月2日目の稀勢の里(太刀持ち松鳳山・露払い輝) |
| ⑨ | 19年3月6日目の朝青龍(太刀持ち朝赤龍・露払い高見盛) |
| ⑩ | 24年9月12日目の白鵬(太刀持ち安美錦・露払い旭天鵬) |
| ⑪ | 27年9月2日目の鶴竜(太刀持ち勢・露払い時天空) |
| ⑫ | 27年11月2日目の白鵬(太刀持ち千代翔馬・露払い大栄翔) |
| ⑬ | 29年11月2日目の日馬富士(太刀持ち宝富士・露払い安美錦) |
| ⑭ | 29年1月初日の日馬富士(太刀持ち宝富士・露払い大翔丸) |
| ⑮ | 27年11月2日目の鶴竜(太刀持ち勢・露払い蒼国来) |
| ⑯ | 29年11月初日の日馬富士(太刀持ち宝富士・露払い安美錦) |


































 左の白鵬(⑫)、右の稀勢の里(⑧)、ともに16の前の恰好だが、見ての通りで異なっている。最近は稀勢の里のような恰好の横綱が多いが、
単に四股を踏むのと反対側の腕を横に出すだけでもいいし、極端なことを言えば、何もしなくても構わない部分だ。
左の白鵬(⑫)、右の稀勢の里(⑧)、ともに16の前の恰好だが、見ての通りで異なっている。最近は稀勢の里のような恰好の横綱が多いが、
単に四股を踏むのと反対側の腕を横に出すだけでもいいし、極端なことを言えば、何もしなくても構わない部分だ。