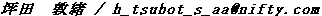| 言わんでもの記 5 |
| 谷風は第4代横綱である。正確にいってみよう。谷風は、明石・綾川・丸山に続く第4代横綱とされている。これは、横綱免許力士の陣幕久五郎が富岡八幡宮に横綱力士碑を建てようとした際に趣意書に載せた代数(初代西ノ海まで)で、現在まで踏襲されている。
今回は、谷風が横綱になったあたりの話をひとくさり。一応「谷風」を題にしているが、小野川もひとくくりにしてしまう。 谷風が横綱免許を受けたのは寛政元年(1789)11月である。いまさらの話ではあるが、宝暦13年(1763)の「古今相撲大全」に載る江戸勧進相撲の起源は、寛永元年(1624)とされている。 指に唾して「大全」をめくり、ついでに眉にも唾つけたまま進んでみる。ということは、江戸勧進相撲に限ってみても、ここまで165年の歴史を刻んでいるはずなのだ。 であったれば、谷風より前に3人いても不思議なことではないばかりか、「明石と、丸山、綾川の間に一人も横綱がいなかったという根拠もない。 むしろ、横綱免許を受けた力士が何人かいたと考えるほうが自然である」(*1)という記述が出てくるのも無理からぬ話である。 (参考)木村政勝「古今相撲大全」宝暦13年 (*1)「「横綱」をめぐる問題点」(読売新聞「大相撲」臨時増刊「古今大相撲事典」読売新聞社所収、昭和55年) 谷風の前の横綱とされる丸山と綾川については、「尤も其の儀は先年丸山権太左衛門、綾川五郎次などゝ申すもの共、右横綱の伝授申請候儀に御座候、尤も記録等焼失仕り御座なく候得共、古き年寄共申伝ひ来り候儀に御座候」(*2)というのが唯一の根拠である。 これは谷風に横綱を授ける際に年寄連が寺社奉行に出した文書の一部である。それに先立って内々に諮ったところ却下されたので、前例と称して2人の名を載せたという具合で、それ以外に横綱であったという根拠は見つけられないということもあり、 まさしく前例と「称して」掲げたという以上の意味がないものと考えられる。なお、「横綱」というのは現在まで連なる白い横綱を暗黙のうちに指してきた。 それより先に黒白の横綱が存在したらしく、安永(1772〜81)頃までの力士の絵に見られるが、寛政元年から遡ること10年ほどだというのに先例とされていないところなどから、現在まで続く「白い横綱」と同列には見ない。 明石に至っては、「いたのかいないのか?」「何人いたのか?」という次元の話にまで落ちてしまい、もうどうにもならないという為体になってしまう。 (*2)根岸治右衛門家秘蔵文書(引用元:古河三樹「江戸時代の大相撲」、国民体力協会(大相撲鑑識大系第3巻)、昭和17年) こうなると、丸山までの3人は横綱免許を受けていなかった、または現在までつながる横綱と同じものは受けていなかったという線が濃厚となろう。 新田一郎氏の「相撲の歴史」(*3)から引用すると、こうなる。 (*3)新田一郎「相撲の歴史」講談社(講談社学術文庫)、平成22年(原書:山川出版社、平成6年)
「相撲起顕」は江戸相撲の番附版元であった三河屋治右衛門が出した書で、番附と勝負附をまとめたものである。 天保9年(1838)から安政元年(1854)の間に十輯まで刊行された。昭和60年にベースボール・マガジン社が復刻している。 一方、老齢の好角家の弁は、どの書物に記載されてあるのかまで書かれることが稀である。ここでまず2つばかり引いてみることにしよう。
1つ目は「きゝのまにまに」(*4)の一巻にあるもの。これは喜多村信節が編年体に編集した史料集であり、 著者自身はそもそも天明3年(1783)頃の生まれだから老齢なわけもなく、元ネタがあったことが容易に推測できよう。 2つ目は「宝暦現来集」(*5)巻之四に載っている。山田桂翁が宝暦から天保までの巷談を記録したものであるが、 恐らく文化以前の記事はこれまた元ネタの存在が考えられる。著者の生年は宝暦10年(1760)というから、これも老齢と呼ばれる資格(?)はあるまい。 ただこの2つ目のほうは、「相撲」連載「歴代横綱正伝・小野川喜三郎伝(中)」に引かれていて、「この八十歳の著者は」(*6)と言っているが、八十歳の年齢を示すものはない。 単純な勘違いだろうか?さらに、これを引用するに当たり「近世風俗見聞集」から引いたという体裁を取っているが、 この「近世風俗見聞集」とは大正元年から2年にかけて国書刊行会から刊行された4冊ものであり、慶長から慶応に至るまでの風俗や巷談風説を記した書13種の集合体であるから、 引用の仕方としては必ずしも適切ではない。それはともかくとして、元ネタがはっきりしないため些かの弱さは感じさせるが、 下の世代の者が敢えてさかしらを加えるということも考えにくい以上は、信頼性が大きく下がることもまた考えにくいだろう。 (*4)喜多村信節「きゝのまにまに」嘉永6年以降(活字本:三田村鳶魚校訂「未刊随筆百種」第十一、米山堂、昭和3年) (*5)山田桂翁「宝暦現来集」天保2年(活字本:森銑三・北川博邦監修「続日本随筆大成」別巻6、吉川弘文館、昭和57年) (*6)池田雅雄「歴代横綱正伝13 小野川喜三郎伝(中)」(「相撲」昭和47年1月号、ベースボール・マガジン社所収) ということで、ここで寛政元年に本当に80歳だった人の随筆を探してみよう。そうすると、こんな記述が出てくる。
「翁草」(*7)巻之百七十八に載る「相撲故実并行司家の由緒」の、吉田司家由緒書を除く全文である。 著者の神沢杜口は宝永7年(1710)生まれなので、寛政元年には数えで80歳になっている。谷風と小野川に紫の廻しを許されたが、 これまで讃州谷風をはじめとする名高い力士たちに与えられたなんて話は聞いたこともないのに、大したことのないこの両人に免許というのもねぇ、というのがその中身。 ただ、のちに稲妻が紫の化粧廻しと注連縄を同時に五條家から免許された例があるところから、この谷風と小野川とに与えられた紫の化粧廻しも横綱とセットだと考えられたことがあったようで、 ともすれば、「八十歳の著者」というのはこの神沢杜口のことなのかもしれない。神沢杜口はこの「翁草」を友人に貸し出していたといい、いくつかの写本があるところから、ことによると「きゝのまにまに」や「宝暦現来集」の元ネタはこれか?という可能性も僅かながらある。 もっとも、「紫の化粧廻しと横綱との違い」や「京都(神沢杜口は京都の人)と江戸との距離」などを考える必要があるのだが。 いずれにせよ、谷風や小野川より前の強い力士に対して、横綱なり紫の化粧廻しなりの免許が下るといったことはなかったようである。 どうして横綱なんてものが必要になったのかについてはここでは立ち入らないことにするが、横綱第一号は結局のところ谷風だったということになるだろう。 (*7)神沢杜口「翁草」寛政3年(活字本:日本随筆大成編輯部編「日本随筆大成」第三期24、吉川弘文館、昭和53年) 上記「翁草」では、谷風も小野川もかつての名力士と比べたら大したことはないと言っている。実際のところはどうだったのかは分からないので、これはこれで真実を伝えている可能性もあるのだが、いつの世も懐古趣味はあるもので、谷風にまつわる懐古趣味も数々ある。 ほんのついでに、いくつか出してみよう。まずは谷風よりあとの世代から見て。 これは「誹風柳多留」百六十七篇(*8)に載る川柳、天保9年(1838)のものである。誹風柳多留シリーズの最後の最後に引っ掛かったという感じ。 この頃、強豪としてその名を今に伝える第7代横綱稲妻雷五郎がいたのだが、この老翁には40年近く前の若き日に見た谷風こそが懐かしいようで、 かつての血沸き肉踊る興奮が、深く刻まれた皺を踊らせている。 (*8)「誹風柳多留百六十七篇」天保9年(活字本:岡田甫校訂「誹風柳多留全集(十二)」三省堂、昭和53年) この僅か6文字のインパクトは絶大である。まさに全否定。「摂陽奇観」(*9)巻之五十に出てくるこの評語は、文政8年(1825)6月6日初日の大坂勧進相撲の記録で、 東西の大関であった四ッヶ峰と小柳(のちの阿武松)に対しての言らしい。別に谷風と比べているわけではないとはいえ、谷風・小野川・雷電・玉垣・柏戸と見てきた浜松歌国にとっては大した相撲ではないと思えたのだろう。 (*9)浜松歌国「摂陽奇観」天保4年(活字本:船越政一郎編「浪速叢書」第六、浪速叢書刊行会、昭和4年)
「道聴塗説」(*10)第十編に載っているこれは、文政8年10月に江戸芝神明社境内で行われた勧進相撲の様子である。 たいへんな好景気で、場所後の公開稽古相撲も引き続いて大入りだったという。関脇の小柳や小結の稲妻が評判高く人気を集めたようだが、 それでも谷風の頃には遠く及ばないといわれたのだそうな。しかも「あの頃は傑物が続々と登場したのに」と言いたいようだ。 従って厳密には谷風との比較ではないのだが、この当時は東でも西でも相撲に一抹の物足りなさを感じて過去を懐かしむ風潮があったようだ。 (*10)大郷信斎「道聴塗説」文政12年か(活字本:国書刊行会編「鼠璞十種」第二、国書刊行会、大正5年)
「天明紀聞」(*11)は成立した年も著者も分からないのだが、この内容は恐らく谷風が活躍した時代の雰囲気を伝えているだろう。 同時代の者が「かつてこれほどの力士はいない」と誉めているもので、懐古趣味とは対極にある。しかもこれは天明3年(1783)11月のことである。 横綱を受ける6年前でこの大評判、とすれば、年齢的(寛延3年(1750)の生まれ)には力量がこれ以上増すことは考えにくいとは言うものの、さらに声価が高くなったであろう寛政期にはどういった評価だったものか。 (*11)「天明紀聞」(活字本:三田村鳶魚校訂「未刊随筆百種」第四、米山堂、昭和2年)
再登場、「翁草」(*12)の巻之百四十一「古角力取」から、末尾だけを引っ張ってみた。この筆者が相撲を見始めた頃には、山颪嶽右衛門やら雷電源八やらが活躍していたという。 このご両人は元禄から享保にかけての相撲取りだから、西暦に直せば1700年代初頭で享保元年が1716年ということになる。つまり幼時の記憶ということになろう。 この段は長文にわたるが、大部分が延享まで(延享から宝暦に改元となったのが1751年)のことで、そのあとに出てくるのは釈迦ヶ嶽ただ一人。 「夫より後」とは「釈迦ヶ嶽より後」の意味なので、少なくとも筆者神沢杜口にとってこの30年間の相撲には魅力を感じられなかったのだろう。 谷風はまあいいとして、小野川などは大いに見劣りがするとして斬って捨ててしまうのだ。さらに既出の「翁草」の記述では、谷風さえ大したこともないと言い切るのだから恐れ入る。 同じく「古角力取」から、現代相撲つまり寛政相撲を容赦なく攻撃している部分をまた引いてみる。
当時とは「現代」のこと。神沢杜口は京都の人なので、江戸相撲の番附で考えてはいけない(江戸では宝暦7年(1757)から番附の形態が変わっているからなおさらのこと)。たまたま見ることができたもので比較すると、享保17年(1732)閏5月の京都番附(*13)によれば「前頭」頭書が15枚、時代が下って寛政2年(1790)5月の大坂番附(*14)では52枚(いずれも東方について勘定)と、かなりの差がある。 そして番附に出ている人数も大幅に増えている。とはいえ、この謎を解こうとすると、「興行主体の確立」と「育成機構の確立」とについて考究しなければならないのではないか。 あまりしっかりとした知識がないので想像されることを並べるだけに終わってしまうが、諸国の有力な相撲取りが招かれて打たれていた興行から、彼らの弟子も出場する興行への変化が考えられるだろうし、 相撲取りやそれらを育てる師匠を束ねる主体の組織化により、規模の大きな興行が可能になったということもあるのだろう。 (*12)神沢杜口「翁草」寛政3年(活字本:日本随筆大成編輯部編「日本随筆大成」第三期23、吉川弘文館、昭和53年) (*13)新田一郎「相撲のひみつ」朝日出版社、平成22年所収写真版 (*14)飯田昭一編「史料集成 江戸時代相撲名鑑」日外アソシエーツ、平成13年所収写真版
これもまた過激というしかない評価だが、筆の主が上田秋成だと知ると、得心もいこうというものだ。「胆大小心録」(*15)138段に載っている。 同じ段の中に讃岐の谷風も混在するので読みやすくはないが、そのうち仙台谷風の部分だけを引いた。現代の相撲取りは小さいとて歎き、 谷風は相手が弱いから第一人者なのだとこき下ろす。それどころか、力と智恵がある子供のようなもので、(本当の)相撲取りではないのだそうな。 ここまでくれば、相手を言い負かすに足る確実な論拠が手許にあっても、言い返すのも馬鹿らしくなってくる。「胆大小心録」の成立は文化5年(1808)で数え75歳のとき、秋成が歿する前年のことであった。 (*15)上田秋成「胆大小心録」文化5年(活字本:上田秋成全集編集委員会編「上田秋成全集」第九巻、中央公論社、平成4年) 懐かしむことへの執念の凄まじさ(?)を見たところで、冷静になってみよう。そのために、新田一郎氏の「相撲の歴史」に載るコラム「昔の相撲は強かったか」を読まれることをお勧めしたい。 「力」や「技」の優劣だけでなく、体格の違いや土俵の違いも考えなければならないのだから、複雑すぎて持て余してしまう。 仮に横綱双葉山が現今のかましを毎日受け続けたとして、名を馳せたあの二枚腰が持ち堪えられるのかどうかという疑念は拭えない。 そして双葉山がどう対処するかという方向に話が進んだところでちょっと落ち着いて考えると、取り口まで変わってしまうともはやそれは双葉山ではなくなるのでは?ということになりかねない。 面白いかもしれないけれど、難しすぎる。最悪の見本を最後に載せて、おしまいにしよう。 (参考)新田一郎「相撲の歴史」(同上)
洒落本「粋庖丁」(*16)巻之三「世わたりは」の一部。長歎息。 (*16)狼狽山人(富土卵)「粋庖丁」寛政7年(活字本:洒落本大成編集委員会編「洒落本大成」第十六巻、中央公論社、昭和57年) (平成22年8月23日起稿、9月4日脱稿)
|