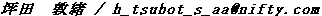| 言わんでもの記 6 |
| 結論の出ない駄文、今回書いてみるのは、捻じる足技「河津掛け」のことである。関脇陸奥嵐や大関貴ノ浪の得意手としてご記憶の方も多いだろう。
現行82手の中で唯一「人名」が技の名に登場する、ということになっている…早くもトーンダウン。 とっかかりとして、現在「河津掛け」がどのように認識されているかを見てみよう。そのためには「相撲大事典」(*1)に当たるのが至当といえよう。 (*1)金指基(財団法人日本相撲協会監修)「相撲大事典 第二版」現代書館、平成19年(初版:平成14年)
実態としては、腕で抱えるのは首でなくても腕でもいいし、廻しを取っていても全然構わなくて、内側に足をかけて捻り倒すと河津掛けになっている。 そして、曾我物語に由来するという説もあるということも紹介してはいるが、ここで最も重要なのは「説もある」であって、「由来する」と決めてかかってはいないということだ。 試みに、曾我物語(*2)を引っ張ってみる。本文の系統が複雑でややこしい話があり、筆者は実際とてもついていけないのだが、大雑把に「真名本」「大石寺本」「仮名本」に分かれ、仮名本も甲類と乙類に分かれるそうだ。 ここでは仮名本乙類を選ぶ。なぜならば、仮名本乙類は流布本に相当するというからで、相撲の技名が曾我物語に由来するとすれば、それは恐らく一般に流布した本によるものと考えるのが最も自然だと思うからである。 なお、該当するエピソードはどの系統の本文でも第一巻に出てくるもので、伊豆に流されていた源頼朝を慰めるために巻狩が企画され、その宴会(打ち上げか?)で行われた相撲大会の最中、俣野五郎景久が勝ち続けたが、 それに対した河津三郎祐泰が俣野を捻じり倒して連勝を阻んだ。すると俣野は「木に躓いた」と主張して再戦を望む。何しろ俣野は京で修行して「日本一番」と称えられた男だからプライドがある。しかも、俣野派の者からか、作戦までも授けられての再登場であった。 (*2)「曾我物語」鎌倉時代後期〜室町時代初期(活字本(流布本):御橋悳言「曾我物語注解(御橋悳言著作集 三)」続群書類従完成会、昭和61年)
ちなみにこのあとはおっとり刀の乱闘である。あまりに素っ気ない勝負、プロ中のプロが技も知らぬ新参者に惨敗したもので、その衝撃は恐らく昭和59年9月に小錦が千代の富士を突き飛ばした一番に似るだろうか。 その手捌きはといえばだ。河津が右手で俣野をつかんで持ち上げ、しばらくして恐らく右横に右腕を振るって吹っ飛ばしたというものだろう。だから決まり手でいえば掴み投げということになるだろう。 足技は途中経過においても全く出てこない。むしろ掴み投げを「河津投げ」と命名したいくらいだ。 こんな状態だからか、河津掛けを語る相撲書は、さながら論争の様相を呈した。これがなかなか面白いので、時代順に並べてみることにしよう。 それが本稿のそもそもの目的である。それではまずは享保7年(1722)の「相撲伝書」(*3)から。 (*3)木村守直「相撲伝書」享保7年(活字本:岩本活東子編「燕石十種」第五巻、中央公論社、昭和55年)
出ている図は現在の河津掛けの解説に登場するものと同様であるが、足を内搦みに掛けている方の力士が宙に浮いている(以下、ここに取り上げる相撲書に出てくる図はみなこの構図である)。また、「河津掛け」という言葉は出てこない。 その内容はどちらかというと掛け方の技術論に終始している。「河津掛け」の語がなかったと考えられなくもないが、そうすると、次に出す延享2年(1745)の「相撲強弱理合書」との整合性の点で少しばかり問題になってくる。 (*4)木村守直「相撲強弱理合書」延享2年
「相撲伝書」から23年、ここで「河津繋」が登場してきた。どうして同じ著者の書でありながら、一方にしか出てこないのか、どうにも分からない。 「古来より」と言っていればなおさらのことで、まさか「古来」が20年弱ということでもあるまい。そして、河津掛けの名称は河津祐泰の得意手だったことによると説明しているのが特徴である(しかも、曾我物語の記述は嘘だと言い切る)。 実はこの書、もう一つこういう記述がある。
どこからどう見ても河津掛けそのもの。どうしてこう分かれて出ているのか、筆者の理解が及ばない。 ここからが佳境である。河津掛けは河津祐泰の得意手なのだという木村守直の説に対し、18年を経た宝暦13年(1763)になって、真っ向から異を唱える論が現れた。 これが名高い江戸時代の相撲全書「古今相撲大全」(*5)なのだ。 (*5)木村政勝「古今相撲大全」宝暦13年
言わんとしていることは次の通り。
(参考)源師時「長秋記」天永2年8月21日条(活字本:増補史料大成刊行会編「長秋記 一」、臨川書店(増補史料大成)、昭和40年)、 「今昔物語集」保安元年前後(活字本:小峯和明校注「今昔物語集 四」岩波書店(新日本古典文学大系)、平成6年)、 「源平盛衰記」鎌倉時代後期〜室町時代初期(影印本(慶長古活字版):渥美かをる解説「源平盛衰記 第四冊」勉誠社(古典資料類従)、昭和53年)、 藤原明衡か「新猿楽記」平安時代後期(活字本:山岸徳平他校注「古代政治社会思想」岩波書店(日本思想大系)、昭和54年)、 経覚「経覚私要鈔」宝徳4年5月4〜5日条(活字本:高橋隆三・小泉宜右校訂「経覚私要鈔 第三」続群書類従完成会(史料纂集)、昭和50年) 10年後(安永2年(1773))の「相撲図式」に出る図(巻三の「かはづがけ」)も、これまでのものと変わらない。 さらに10年余り経過して古今相撲大全に喰ってかかろうとしたのが、天明5年(1785)序の「相撲今昔物語」だ。その所説をご覧に入れよう。 (参考)伊東義眞撰「相撲図式」安永2年(復刻本:「稀書複製会叢書」米山堂、昭和5年) (*6)子明山人「相撲今昔物語」天明5年(活字本:国書刊行会(朝倉夢声か)編「新燕石十種」第六巻、中央公論社、昭和56年)
最後転失気とは「最後っ屁」のこと。これは、「古画」の構図をもとにし、吊ったのが俣野で吊られたのが河津であるとして、 吊られた河津が足を掛けているのだから河津掛けだ、という主張である。そして吊られた側はほぼ負けなのだから、最後の悪あがきとして、反ってみれば、足が外れなければ勝てるかも、というのだ。 技術的にはそうなのだが、「古画など」の「など」には曾我物語が含まれていない様子で… 時代は100年飛んで、明治。初代梅ヶ谷が横綱免許を受け、天覧相撲が行われた頃、相撲書の出版も盛んになった。 その中から、明治18年の「古今相撲大要」(*7)の記述を引いてみよう。 (*7)岡敬孝「古今相撲大要」明治18年
技の説明は現在言われているものと等しい。河津の称については古今相撲大全の説より踏み込んで誤りとしており、それだけでなく絵の方は「蛙掛」を見出しとしているのも特徴である。 また、相撲今昔物語の説は、目に触れていないのか斥けたのかは定かではないが、採られていない。 本稿の題は「Kawadzu-gake?」である。要するに「河津掛け」なのか「蛙掛け」なのか、ということなのだが、 旧仮名にすればいずれも「かはづがけ」になるものの、新仮名であれば「かわづ」と「かわず」。ローマ字で書くと「Kawazu」で良さそうな気もするけれど、 現今のコンピュータで日本語を入力するに当たってこう打てば「かわず」になるし…ということで、どっちつかずの意味を込めて「Kawadzu」という表現にしてみた。 ここまで並べてみた通り、江戸時代に少しもめた…らしい河津掛けも、明治に「蛙掛け」の表記を採った書があるというのに、気がついてみれば今もやはり「河津掛け」の表記を用いている。 結局は「蛙」より「河津」、というよりも「曾我物語」の挿話のインパクトが大きかった、ということなのだろうか(河津は(そして俣野も)そんな技を繰り出していないのに)。 そうだとしたら、河津が勝者だからか、それとも河津が斬り殺されたからか、はたまた河津の息子たちによる仇討ち話が人口に膾炙したからか。 それとも、相撲今昔物語に出てきた「古画」のせいなのか… (平成22年12月3日起稿、同4日脱稿)
|