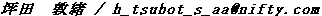| 言わんでもの記 7 |
| 前回「よく分からない」ということを滔々と語り続けたが、しつこくもまだ続ける。今度は、「曾我物語」の諸本に出てくる手さばきを並べてみようという魂胆だ。前回掲げた流布本の場面に対応するところを、他の諸本で眺めてみる。 まずは真名本(天文15年(1546)書写妙本寺本)(*1)からいってみる。ちなみに流布本に出てくる俣野への作戦伝授はなく、河津は「まぁ見てなって」といった感じで自信満々で再登場してきている。 (*1)「曾我物語」鎌倉時代後期〜室町時代初期(活字本(妙本寺本):角川源義編「妙本寺本 曾我物語」角川書店(貴重古典籍叢刊)、昭和44年) (参考)「曾我物語」同上(影印本(妙本寺本):「真名本 曾我物語」勉誠社、昭和49年)
真名本である以上当然ではあるが、あまりにも読みにくいので、大石寺本(*2)も続けて出す。 (*2)「曾我物語」同上(活字本(大石寺本):梶原正昭・大津雄一・野中哲照校注及び訳「曾我物語」小学館(新編日本古典文学全集)、平成14年)
真名本を一部簡略化して読み下したのが大石寺本という位置づけで、その中にもさらに省略があるものがあるそうだが、ここに引いた新編日本古典文学全集本は、原態をとどめるという日本大学総合情報センター蔵本を底本にしている。 この場面については忠実に訓読していると思われる。分かりにくいのは「相括り」と「腹白」だろうか。 「相括り」は見当がつきかねる。新編日本古典文学全集本の註では「未詳。相手の体や手足に自分の手足を絡めて、絞り上げるようにして動きを封じようとする技か」とする。 「腹白」も同じく註を読めば「のけぞって腹を突き出す姿勢になり無防備になること」とあるから、平成15年3月の千秋楽、大関千代大海の突っ張りに横綱朝青龍が腹を出して完敗した場面でも想像すればいいのだろう。 ということでその相撲ぶりは、まず河津が俣野の喉を突っ張ると、俣野は見ながら捕まえようとするので、河津は片手で外から足を取りながらもう一方の手で突いた。俣野はのけぞった。 河津は飛び込んで右手で後ろ褌を取り、強烈に引きつけるなり持ち上げ、そのまま暫し差し上げておいてから2回ほどくるくる廻してドッと落とした、ということになろうか。 続いて仮名本を出してみよう。甲類と乙類に分かれ、乙類は前回に出してあるので、甲類の本文を引こう。 甲類の中で最も古い様態を示すという太山寺本(*3)をここでは用いる。 (*3)「曾我物語」同上(活字本(太山寺本):村上美登志校註「太山寺本 曾我物語」和泉書院(和泉古典叢書)、平成11年) (参考)「曾我物語」同上(影印本(太山寺本):「太山寺本 曾我物語」汲古書院、昭和63年)
和泉古典叢書本は校註者が漢字を多数当てて読みやすくしてあるので、こちらを採った。原態については影印本を当たられたいが、漢字があまりにも少ないので、慣れなければ甚だ読みにくい。 手さばきは真名本と少し異なる。ちなみに前回引いた仮名本乙類(流布本)では再戦の前に俣野が作戦を授けられているが、これはこちらの仮名本甲類でも変わらない。 そして俣野は後ろ褌を取ろうとしながら相手の動きを観察した。河津は腕を引いた恰好をしながらであろうか、俣野にするすると近寄り、俣野が恐らく横への動きで抜けようとしたところ、河津は右腕を伸ばして前褌を取った。 真名本では後ろ褌であったが、こちらでは前褌である。いずれにしても右で廻しを取って引きつけたのだ。俣野はむやみに動くと腰も廻しもちぎれそうなのでただ立ち竦むよりない。 ややあって、河津は相手を引きつけたかと思う間に目よりも高く持ち上げて、持ったまま1回廻り、片手を離して叩きつけた。乙類(流布本)では1回廻る描写はなく、半時ばかり持ち上げておいて落としたとされているが、それ以外には大差はない。 真名本と仮名本で共通することは、右手一本で廻しを取って高く持ち上げ、それから落としたということである。 そしてもう一つ、忘れてはならないことがある。曾我物語の諸本は数多あって博捜というわけにいかず、それゆえ断言することは憚られるのかもしれないが、 重大な共通点としては、「足技が出てこない」ということだ。「河津掛け」は足技である。それが痕跡さえも窺われないことに注目すべきであろう。 前回引いた「古今相撲大全」や「相撲今昔物語」で足を掛けたのは河津だ俣野だと言い合っていたが、それも空しいばかりで、「古今相撲大要」の著者は慧眼の持ち主だった、ということになる。 どこから足技が出てきたのだろう。分かりっこないと言ってしまえばそれまでだが、「相撲今昔物語」が「また古画などをみるべし」と言っているのに一応従ってみようか。 といっても、美術史の知識は皆無なので、河津と俣野の取組をモチーフにした絵がどれくらい描かれているのか、そしてその嚆矢となった作品は誰の手になるいつごろのものなのか、まるで見当もつかない。 ただ、こんな絵があるので、紹介しておこう。狩野山雪画「武家相撲絵巻」(*4)で、相撲博物館に蔵されている。島根県立古代出雲歴史博物館で平成21年7月17日から9月23日まで行われた特別展「どすこい 出雲と相撲」の図録にカラーで収められているので、 可能であればご覧になられるとよいだろう。「列品解説」によれば、「狩野山雪(一五八九〜一六五一)は江戸時代初めの狩野派(京狩野)の絵師。当絵巻は二部に分かれており、前半は皇位継承相撲、後半は河津三郎祐泰と俣野五郎景久の相撲が描かれている」という。 皇位継承相撲は、文徳天皇の後継を惟喬親王と惟仁親王とで争い、相撲で(といっても親王本人が取ったわけではない)決着をつけたという逸話のことであり、平家物語(及び源平盛衰記・源平闘諍録)や曾我物語(真名本のみ)に出る。 そして河津と俣野との相撲は2番描かれている。それはつまり、木に躓いたと俣野が主張したものと、俣野が持ち上げられて敗れ去ったものとである。 前者は俣野が左膝を着くことによって示されているが、後者はといえば、河津が右で前褌を掴んで持ち上げんとするのを、俣野が左腕を河津の首に巻きつつ右腕をいっぱいに伸ばして空を掻きながら、左爪先を河津の右膝裏に掛けて必死に堪えんとする形で描かれている。 そう、これは前回出した種々の相撲書で河津掛けの絵として出ているものとよく似ているのである。俣野が右腕を伸ばしていなかったり、俣野の左足が爪先だけでなくもっと搦んでいたりという違いはあるが、 これらの図の祖形なのでは?と思わせるものである。この武家相撲絵巻の成立は、前回掲げたどの相撲書よりも古い。それは狩野山雪の歿年からして明らかである。 ちなみにこの絵には詞書もある(絵巻なので、詞書はあるのが普通)。絵の上方を雲のように覆うこの場面の文章は、曾我物語の仮名本乙類(流布本)そのものである。 つまり、俣野は半時ばかり河津に右腕一本で持ち上げられ、そして落とされたという内容で、俣野が足を使ったことにはなっていない。 半時ばかり持ち上げられている間、俣野が左足を掛けて粘ったのかもしれないが、文章にそれは表現されておらず、寧ろ狩野山雪がそういう想像を膨らませたのではと考えたい。 そして視覚に訴える絵のインパクトが勝り、河津掛けの絵として一般的に使われるようになったという流れなのだろうか。 本来であれば「蛙掛け」の発生と「河津」との混淆とを探る必要もあるのだろうが、「蛙掛け」を語る材料がなく、これは断念せざるを得まい。 (*4)狩野山雪「武家相撲絵巻」江戸時代(島根県立古代出雲歴史博物館「どすこい 出雲と相撲 特別展図録」ハーベスト出版所収、平成21年) ここで疑問の品が1つあるので、つけ加えてみる。まずはその本文から。
曾我物語の真名本と仮名本乙類とを交ぜたような本文ではあるが、俣野の足技がしっかりと記載されている不思議な内容である。 これは「曾我両社八幡宮并虎御前観音縁起(別名・曾我両社縁起)」(*5)で、続群書類従に収められている曾我八幡宮の縁起。 曾我八幡宮はいくつかあるが、これは静岡県富士宮市上井出に鎮座する八幡宮のこと。内容について「群書解題」(*6)の記述に拠ると、 (*5)「曾我両社八幡宮并虎御前観音縁起」室町時代?(活字本:塙保己一編、太田藤四郎補「続群書類従(訂正3版)」第三輯上、続群書類従完成会、昭和34年) (*6)続群書類従完成会編「群書解題(13巻本)」第六、続群書類従完成会、昭和61年(元版:続群書類従完成会編「群書解題(26巻本)」第一下、続群書類従完成会、昭和38年)
後半を略した。曾我物語の内容に近く、曾我物語の成立時期が室町時代と考えられていること、八幡宮の造営や虎御前の死亡よりも曾我物語の成立が遅いことから、 本縁起も室町時代の成立と見ていることが窺える。とすると、俣野が足を掛けて抗おうとするこの記述はどう説明できるのか。 筆者が見ていない曾我物語の諸本には出てくるのかもしれないが、あるいはこの縁起が実はそんなに古いものではないのでは?という疑いを懐かしめる記述である。 最後は蛇足。ここまで蛙がなかなか出てこなかった。蛙と相撲といえば、鳥獣戯画(*7)だろう。おぼろげながらでも、蛙が相撲を取っている絵を思い浮かべられる方もあろう。 ここにその絵を出すことは難しいので、何としても目にしたい方は、新修日本絵巻物全集をはじめとして複製が各種出ているのでそれをご覧願いたい。ではさようなら、というのもあまりにもつれないので、文章でその模様をお伝えする。 意外な人が残した文章があるので、お読みいただこう。 (*7)伝鳥羽僧正「鳥獣戯画」平安時代後期〜鎌倉時代初期(田中一松監修「新修日本絵巻物全集」4、角川書店所収、昭和51年)
傍点があるが省略した。鳥獣戯画の複製を入手して、うち眺めて愉しんでいるその主は、なんとノーベル物理学賞受賞者の朝永振一郎である(*8)。 ここで挙げている特徴は、(1)蛙が右外掛けをやりながら兎の急所というべき耳をくわえるというその取り口、 (2)兎の応援と蛙の爆笑、(3)((2)にも関連するが)時間経過に伴う相撲の推移、のようにまとめられよう。 (*8)朝永振一郎「鳥獣戯画」(「朝永振一郎著作集1 鳥獣戯画」みすず書房所収、昭和56年(初出:「暮しの手帖」昭和51年11・12月号、暮しの手帖社)) (1)について今村みゑ子氏の文(*9)で記せば、「兎が二匹笑いながら声援を送っており、その先はがっぷり組んだ兎と蛙の相撲である。兎は長い両耳を蛙に噛まれ、空に向けた口から舌を出して悲鳴を上げている。蛙のずるい手で、これも兎の特徴である長い耳にちなむ戯れである。(中略)蛙は右足を兎の左足に外掛けに掛けている。と、次の瞬間、兎が投げ飛ばされて背中を地に着け、両足が宙に踊る」となる。 「蛙のずるい手」とはまったくその通りで、髷を引いて反則負けになる場面をつい思い浮かべてしまうのである。 (*9)今村みゑ子「絵巻『鳥獣戯画』を読み解く−戯画の重層性、および「遊び」について−」(今村みゑ子「鴨長明とその周辺」和泉書院(研究叢書382)所収、平成20年(初出:「芸術世界 東京工芸大学芸術学部紀要」11、東京工芸大学、平成17年)) (2)については、もう1つこの鳥獣戯画が持っている大きな特徴があるので、加えておこう。それは、鳥獣戯画は絵巻物に通常存在する「詞書」を持たないということである。 小峯和明氏の「説話の森」の一章「動物たちの声−鳥獣戯画と芸能」(*10)によれば、「この絵巻を見ていて、一番欠落しているもの、いいかえれば、最も想像力を刺激するのは、動物たちの<声>である。さまざまな芸能や遊びに興ずる彼らはいったい何を話しているのか。 見物衆たちはどう感嘆し、笑いさざめいているのか。あるいは、見る側がどこまでそれを想像できるかが試されているような気がする」となる。 これを念頭において笑いこけている蛙たちを見てみる。再び小峯氏による同章の文(*11)から引くと「たとえば、相撲における蛙が兎をえいやっとばかりに投げ飛ばし、したり顔でそっくりかえり、 投げられた兎もあおむけになったまま笑い、左手の蛙三匹が大笑いしている秀逸な画面。見物の蛙の笑いは、右はしのが立ったまま両手をひろげ、まんなかが座って天をあおいで笑い、左がうつぶせになって笑う。笑いの様態を描きつくしている。まさに蛙の笑い声が直接、響いてくるような形象がたくみになされていて、 見あきることがない。これはあたかも『宇治拾遺物語』にいう「一度にはつとわらひけるとか」に共通する開放的な笑いとみてよい。ことばにすれば、そう表現するほかない笑いである」(途中の改行を略した)。 今村氏(*12)はこれを「笑いの三体図」と呼ぶ。この蛙たちがどのように笑っているのか、朝永振一郎のいう「ワハハハ、ゲラゲラ」だけでなくバラエティーに富んでいるのか、そして笑いながら蛙の勝ちっぷりを讃えているのか、それとも兎の負けっぷりを馬鹿にしているのか、想像は果てしない。 加えて、勝って仁王立ちする蛙の口からは息なのか声なのか、曲線が上に伸びている。こちらは今村氏の文(*13)で。「投げ飛ばした蛙は両手を広げ、両足を踏ん張り、あたかも歌舞伎の「見得を切る」体である。 蛙の大きく開けた口からは息もしくは声の太い線が立ち昇り、「えい、やあっ」、「どうだっ」などと叫んでいるのであろう」。兎を破ったこの蛙、何を思う。 小峯氏(*14)は「試されているのは読者であり、笑われているのは人間の方であるかも知れない」とまで言うのだ。 (*10)(*11)(*14)小峯和明「説話の森 中世の天狗からイソップまで」岩波書店(岩波現代文庫)、平成13年(原書:「説話の森−天狗・盗賊・異形の道化」大修館書店、平成3年) (*12)(*13)今村みゑ子「絵巻『鳥獣戯画』を読み解く−戯画の重層性、および「遊び」について−」(同上) 残るは(3)である。絵巻物は右から左へと描かれていく。蛙と兎との相撲の場面を右から眺めると、兎の応援−組み合う蛙と兎−蛙が兎を投げ飛ばす−蛙の爆笑という順序で描かれている((2)にも関連するとしたのは、兎の応援から始まるからだ)。 2組の蛙と兎とが相撲を取っていると見られないでもないのだが、恐らくは同一の兎と蛙との組による一連の流れであると無意識的に見るであろう。 既に数度登場願っている今村氏の文(*15)をここでも引く。「この場面、蛙と兎の相撲を、蛙と兎が組み合って、次の瞬間投げ飛ばす、という二様の動作を、応援している兎方・蛙方の中央に描いた異時同図である。 しかも、絵巻を右から左へ広げていく時間により、最初に見える兎方の応援はまだ決着がつく前、一方、蛙方は蛙が勝って喜ぶ様子である。相撲の勝敗を連続的に描くために、応援団は絵巻の時間のずれに応じて描き分けられている。全体を見るならば、兎方・蛙方の応援団を左右にして中で兎と蛙が相撲を取る図であるが、絵巻の時間に載せて順に開いていって、リアルタイムに見ることが意図された、まさに今日の映画でありアニメーションである」。 つまり、作者が同一の取組の熱戦とその結末とを連続的に見せるという意図でこのように描いたと考えるものであり、そこにアニメーションの手法の萌芽が見られるとする(なお、相撲の場面ではないが、登場する動物の視線の向きによって各場面を巧みにつなぐ効果を生んでいることも挙げられている)。 (*15)今村みゑ子「絵巻『鳥獣戯画』を読み解く−戯画の重層性、および「遊び」について−」(同上) それにしても朝永振一郎の観察眼の鋭いこと。鳥獣戯画に特徴的とされていることをあらかた網羅していた。と、鳥獣戯画に見入っているうちに、河津掛けの話をすっかり忘れてしまった。 明治33年から相撲記者になった栗島狭衣は明治初期の大関綾瀬川の息子である。今を去ること100年くらい前、彼もまた、河津掛けという名称の出鱈目さにウンザリしていたのだろう。 画家の鰭崎英朋とともに出した「角觝画談」(*16)で、足を掛けたのは俣野であるから(彼は曾我物語を読んだ上でこう言っているのだが、さすればどの系統の曾我物語を読んだのだろうか)、河津掛けの名称が「大に出鱈目である」と言って投げ出してしまい、鳥獣戯画に救いを求めた。 (*16)栗島狭衣・鰭崎英朋「虚実変化 角觝画談」教学院書房、昭和5年(復刻本:ベースボール・マガジン社、昭和60年)
水掛・蛙掛の称については前回の「古今相撲大全」と「古今相撲大要」とを見られたい。まあ、うろ覚えというのは恐ろしいもので、鳥獣戯画での蛙の足技は外掛けである。惜しくも空振りだった。 結局、河津掛けの正体とはなんなのだろう。歯が立たぬ難題であった。筆者が探り探りするうちに、大力河津に「そんな技などないわ!」と片手で掴まれ投げつけられてしまった、というような感じだろうか。 (平成22年1月9日起稿、同10日脱稿)
|