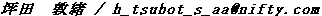| 言わんでもの記 8 |
これ(*1)は蔵前国技館閉館直前くらいの話のようである。大相撲のテレビ中継が始まって30年くらいの頃。 よく「テレビと生とは違う」と言うけれど、これもまた、その違いというものを分からせてくれることのひとつだ。 (*1)竹西寛子「ニュース」(「自選 竹西寛子随想集 1」岩波書店所収、平成14年(初出:「ひとつとや 113」(「毎日グラフ」昭和58年3月20日号所収、毎日新聞社))) 大相撲のテレビ中継は昭和28年夏場所初日(横綱北の湖の誕生日というのは運命なるか奇縁なるか)から始まったが、テレビより遡ること25年、昭和3年春場所初日からはラジオ中継が始まった。 このラジオ中継が開始される前、その賛否をめぐって議論があったことは特に記されてよいことだろう。そして反対論の骨子を推測することは、さして難しくもあるまい。 大相撲アナウンサー第一号の栄を担った松内則三氏の文(*2)から引く。反対論は「国技館から相撲を放送したら、わざわざ寒い思をして、木戸銭を支払ってまで、両国くんだりまで、 足をはこぶものがなくなるだろう。家にいて、火鉢や炬燵にあたりながら、勝負を楽しむ相撲好きが、ふえるに違いない。そうなれば、ただでさえこの経営難に更に輪をかけることになるに違いない。 だから、中継放送の申込みなど絶対に同意はできない」。これはこれで筋が通っている。この場所は、大正14年末に認可された「財団法人」がようやく正式に始動した最初の場所だった。 ましてこの「財団法人化」そのものが経営難を救うための方策の1つであったのだ。これに対峙する賛成論は以下の如し。 「それはものの見方、考え方の(引用者註:脱文か)相撲場の雰囲気や、勝負に移りかわる勝負の模様を刻々に伝えてゆけば、家の中にじっとしていられなくなるだろう。 かえって相撲の放送で、大きな刺激や興奮を感じさせて、いわば眠っている相撲ファンの熱を呼び起し、相撲場へお客さんを誘い出す糸口を作る結果になるだろう。 これが人情だ。だから、中継放送は大いにやる必要がある。せっかくこの新しい文明の利器を、利用して放送を申込んで来たのだから、受入れるべきである」。 激論を経て勝ちを占めたのは賛成派だ。放送席として向正面(正面ではなく)に座を占めて、昭和3年1月12日に第一声が発せられた。 以来80年余、浮沈あったりといえども、歴史の上でも賛成派が明確に勝ちを占めたということは、まず間違いのないところだろう。 まずこの場所は後半になって客足が伸びたそうだ。そしてそれが線香花火で終わらなかった一つの要因は、いかに生の相撲場に魅力があるか、ということだろう。 (*2)松内則三「相撲放送 思い出ばなし」(「相撲」昭和34年1月号所収、ベースボール・マガジン社) (参考)殿岡駒吉「巷説・相撲昭和史 2」(「相撲」昭和46年2月号所収、ベースボール・マガジン社) 魅力魅力とはいうものの、いったいいずこなりや、と訊かれたら、それは各々思うところがあろう。 筆者の場合であれば、眼前で繰り広げられる相撲技の変転と緩急、それと五感のうち触感を除く4つで感ずる相撲場の雰囲気、さらに加えるならば独特の間合い、ということになるだろうか。 逆に、結果としての星の白黒には興味がない。結果だけを知ろうとすれば、ニュースで容易に知ることができるし、何より相撲を見る必要がないのだから意味がなく、つまらないのだ。 優勝争いにしても、のちのちにその経過を簡単にたどって本場所の経過を思い出す手がかりとするには便利なのだが、所詮は星の数で決まるもの、やっぱりあまり惹かれるものがない。 勝敗を気にするのは、地位と生活とがかかっている力士本人、その家族、そして贔屓力士がいる人たちぐらいでいい、と思ってしまうのだ。 相撲場へ近づく。力士幟が彩り豊か、風にはためくその向こう、そこは非日常の空間だ。門となるは正面木戸口、日常空間との橋渡しとなる唯一の場所。 もし朝ならば、櫓太鼓の撥の音、この冴えた響きに誘われて、ふと気がつけば木戸口は我が背にあった。頭上なる扁額に「国技館」の三文字、その下を歩んで館内へ。 会場によって違いはあるが、目の前には各種賞品、いくら優勝に強い興味を示さぬとはいっても、まばゆい輝きに目を奪われぬ訳はない。 福岡だったら入ってすぐの売店も賑やか。東京なら茶屋の飾りに季節を感じられる。まず普段お目にかかることのない、たっつけ姿の出方さん、彼らを見るだけでも「ここは相撲場」という気分になれるが、 なによりも行きかう力士の鬢づけの香りこそが、「相撲場に来た!」と思わせてくれるのである。 こうして気分が盛り上がってきたら、席に着いて土俵を見よう。会場によって明るさが違うし、東京以外に優勝額はないけれど、 どの相撲場に行っても、当たり前だが、土俵と屋根はある。屋根…正確には「屋形」…は、別になくてもいいはずだけれど、 なぜかあった方が落ち着きがいい。もともとは単なる雨よけのはずなのに、現在のは昭和6年から続く神明造の凝ったもの。 確かに土俵には神を迎えるのだから、神明造はふさわしいけれど、だとするとその前の切妻造や破風造のは何だったの?と考え出したらきりがないのでやめておこう。 屋根の下には、水引幕と4つの房。もともとは屋外で興行していたのだから、屋根は当然下から支えた。それは4本の柱だった。 時間が経って屋内興行になった。さらに時間が経つと、柱が邪魔だという話になった。ここでバッサリなくしてしまわないところが、不思議でもあり、センスがあるとも言えるところ。 水引幕と4つの房、そして土俵祭が終わったら、房には御幣がくくられて、土俵は神宿る異空間となる。こういう設えや、房の色にまつわる説明は横において、視覚的にも特別な場所なのだなと思うことができれば、この際充分。 土俵はそれこそ主戦場、よく考えればうまくできている。相撲を取るのに、実は土俵はなくてもいい。正確には「勝負を分ける境界線」、これが別になくたって、相撲という競技は成立させることができる。 要するに、現在の相撲から前に攻める技がなくなるだけのこと、のように見える。ところが、境界線ができたことで、しかもそれが円だったことで、相撲技は恐らくかなり大きな変革を遂げただろう。 まず相手を境界線の外に出せば、それで勝てる。相手がそれを堪えようとすると、場合によっては体勢に無理が出る。 ということは、前に攻めると、投げ技なども利きやすくなるのだ。逆に自分が粘っているうちに、相手の恰好が崩れてくることがある。 おまけに境界線が円なので、円周に沿って動けば無限に使える。これらの土俵の特徴を、対戦する両力士がそれぞれ自分の得意に合わせて生かし、相手の得意を生かさせまいとしてせめぎ合う相撲、それが力量がだいたい五分の相手と取った場合や、自分よりも強い相手に善戦するか勝った場合の「いい相撲」ということになるだろうか。 力量に差があると目される対戦でこういう相撲が見られたら、それは見る側からすればもう「儲けもの」である。 順当な場合は、強いほうが自分の得意を表現し尽くして勝つという「いい相撲」になるだろう。だから、全然取るべきところがない相撲や、 相手の得意な相撲を取らせたくないばかりにただごまかす相撲、それから自分の力量が上で相手がやっと抵抗している程度なのにもたつくというような相撲は、評価できないということになるだろう。 つい先走って、「いい相撲とは」を語ってしまった。相撲場へ行って本物の土俵を眺めたら、テレビで見たそれと全然違う大きさに見えることだろう。 いろいろな声を聞いたが、筆者にとっては、テレビで見るよりかなり狭く感じるものである。この狭い領域内で大柄な男2人が動くのである。しかも行司もそこにいる。 これは本当に全身で土俵の広さを覚え込まないと、自体はうまくさばけない。しかし、だ。その狭い土俵の四方、もとは雨水排水用だったといわれる徳俵がある。 わずかに俵1つ分だけ、土俵を広く使えるようになっている。狭い土俵のうちの、それこそ微々たるもの。ところがこれが曲者、相撲を見るのなら、そこにも目を配りたい。 土俵の上、力士はそこに相撲を取るために上がるのだが、相撲を取る前には塵を切り、塩を撒くし四股も踏む。そしてわざわざ蹲踞もする。おまけに力士の頭には髷が結われている。 まだ他にもいろいろとあるけれど、上述のものも含めたこれらの様式性や装飾性(塩と髷には実用的な意味もあるにはあるが)が、大相撲を大相撲たらしめる大きな要素だ。 大相撲はただ単に力と技とを観衆に見せるというだけではなくて、「見た目の美しさ」にも意を用いて成立している興行である。 特に塵浄水や勝ち名乗りの恰好というものには、(人によっては「体をなしていないのでは」と眉をひそめられるようなものもないではないが)個性と呼べるものが滲む。 さらに大きな特徴は、繰り返される仕切りであろう。面白い話が2つあるので、載せてみる。まずは昭和2年春の話(*3)。 (*3)酒井忠正「仕切りさまざま」(酒井忠正「相撲随筆」ベースボール・マガジン社所収、平成7年(原書:住吉書店、昭和29年))
次は栃錦(*4)。ちょっと辻褄が合わない感じも受けるが、そのまま載せる。 (*4)北出清五郎「私が選ぶ昭和の名力士ベスト20<その2>」(読売新聞「大相撲」臨時増刊「古今大相撲事典」読売新聞社所収、昭和55年)
一般には昭和27年夏の関脇時代の話(蹴手繰りからの突き落とし)とされているが、栃錦は25年秋、前頭3枚目のときに東富士を蹴手繰りで倒していることからすると、こちらではあるまいか。 ちなみに初対戦は24年春、東富士新横綱の初日であるから、実質2年弱ということになる。この件を細かく考えすぎると本筋から外れるのでこれぐらいにして、 仕切りというものは、自らの気合を高めながら、相手を考え相手には考えさせ、なおかつ互いに気を合わせていって、合えば立つというものということができる。 ところが、無制限だった仕切りの時間が、昭和3年に幕内10分という制限を課せられるようになり、徐々に短縮されて25年秋からは幕内4分とされてしまった。 この設定は実況中継の開始によるもので、利点としては打ち出し時刻を予想できる(番組編成に好都合)ということが挙げられるが、その反面見逃せない大きな難点を抱えることになった。 「相撲場の愉楽」にそぐわないが、敢えて載せることにしよう。
これ(*5)は昭和29年のもので、他に中尾方一氏も参加した座談会の一コマである。さらに翌年の座談会(*6)になると、既に出てきた松内則三氏が、 (*5)「古今東西相撲話 相撲趣味の会会員座談会」(「相撲」昭和29年8月号所収、ベースボール・マガジン社) (*6)「座談会 相撲観戦五十年」(「相撲」昭和30年6月号所収、ベースボール・マガジン社)
とまで言い切った。確かに、数度繰り返す仕切りの全てに精力を注いでいる力士がどれだけあるか、実に心許ないものである。 そして時間一杯になってから無理に帳尻を合わせようとするから、かえってしわ寄せが出るのだ。同じ座談会で、
と言っているのだが、相撲を知らないという次元の話ではなくて、知らせる内容がないのである。仕切りについては、何とかならないのかと思うことが多い。 少し熱くなりすぎたので、愉楽の話に戻りたい。幕下以下の力士には申し訳ないが、関取の化粧廻しは豪華絢爛、テレビでもある程度は伝わるものだが、これがまた現場で見ると、その色彩美がどういうわけか全然違うのだ。 得も言われぬ鮮やかさ、「目もあや」という句があるが、このことだろう。取り廻しの色といい、力士の肌の色といい、相撲場に行って生で見ると、印象が大きく変わることは間違いない。 化粧廻しを身にまとって観衆に顔見世をするのが土俵入り。俵のぐるりを取り囲む色彩美が見ものである。そうかと思えば、横綱は一人で土俵を独占できる特権があり、しかも太刀持ちと露払いを従者とする。 横綱土俵入りでは、塵浄水、柏手に四股という所作を力強く行うとともに、四股と四股との間に生まれたせり上がりの工夫によって観客をさらに惹きつけることになったのだ。 筆者は実際やりすぎで、横綱ごとの型の違いやら、前回観戦時との差異やらを楽しんでいる。 化粧廻しと並ぶ鮮やかさといえば、行司の出で立ちである。軍配、菊綴や房の色ももちろんだが、何よりも装束の色というものは、取組が行われている土俵ではひとり異彩を放っているのだ。 今でこそ力士の取り廻しも色とりどりではあるが、それ以外には主に肌の色と土の色だけなのだから。 大相撲はことごとに「美しさ」を求めるものだが、行司はその最たるものだろう。毅然たる土俵裁きに優れた高砂部屋の名行司、第33代木村庄之助の弁(*7)である。 (*7)33代木村庄之助「力士(ちからびと)の世界」文藝春秋(文春新書)、平成19年
立ち合ってしまったら行司よりも力士に目が行くのは当然としても、立ち上がる前、力士たちの動きを制するのは行司の役目。 仕切りを合わせるのもそう、さらに遡って力士を呼び上げるのもそうだ。また、相撲が終わったことを示すところからは、行司が主役を取り戻す。 軍配裁きと勝ち名乗り。これら一連の動きと声に美を求められるのが行司である。そういう意味では呼び出しも変わらないのだろう。 残念ながらその芸談は見つけられていないのだが、声もそうだろうし、白扇のかざし方もそうだろう。 それから土俵の整備も重大な仕事で、取組開始から打ち出しまでに限定しても、土俵全体を整えるのと、さりげなく蛇の目を整えるのとがある。 まだあるけれど、大いに目立つのはだいたいこんなところだろうか。せっかく相撲場に行ったのであれば、行司や呼び出しにも目と耳を注いでほしい。 テレビ中継だと、行司や呼び出しが活躍しているときは、取組のスロービデオを流しているか、取組結果を紹介するか、はたまた翌日の取組を紹介するかで、彼らが主役になることはあまりに少ない。 国技館にも前の取組を再度見られるスクリーンを取りつけてほしいなんどという要望が出たことさえあったが、(物言い協議中を除けば)再生するタイミングは力士の呼び上げ中ぐらいしか考えられない。 とすれば、呼び出しと行司による力士の呼び上げは要らなくなってしまいかねないのだから、寧ろやってはならぬことである。 相撲が終わって、次の力士を呼び上げる間というのが、相撲場の雰囲気をつくり出す一つの要素ともなっているのだ。打ち捨てるなど、もったいない。 観客が増えると、果然歓声やら喚声やらが大きくなるが、まだ仕切り中であっても、済んだ相撲を談ずる人、土俵上の力士を論う人、 はたまた桝席の4人で世間話に打ち興ずる人、それぞれの声がない交ぜになり、食と酒が進んでこれらの声は明るく大きくなり、館内を支配するのはさんざめきである。 以前はこれにビール瓶やジュース瓶の音がまじっていたが、最近は缶ビールとペットボトルに取って代わられたような感じである。 そのさんざめきの中を呼び出しや行司の声が通り、逆に激戦や番狂わせのあとはその声も通らぬほどの熱狂の坩堝となるという、こうした一種の綯い交ぜも、相撲場の雰囲気をなしている。 筆者は相撲場で酒はほとんど呑まないが、単独行でなければやはり相撲談義(ことによると、しかつめらしいかも?)、そして(テレビで見る場合ほど詳細にとはいかないが)取り口を追いかける方に比重をおきながら、弁当やら焼き鳥やらを食しつつ雰囲気にも身を浸すという、どっちつかずな楽しみ方をしている。 ここまで、力士の芸、行司の芸、そして呼び出しの芸というものをたっぷり味わい、結びの一番まで無事に終了したら、残すは弓取式だけである。 大相撲見物の最後にふさわしい快味をたたえているのに、非常に残念なことに「視聴率」が低い。 確かに早めに会場を出たほうが「渋滞」に巻き込まれずに済むので、さっさと帰ろうとするのも分かる部分はあるが、締めくくりとして是非見ておきたい。 昭和26年秋までは千秋楽だけだったので稀少価値もあった。現在は毎日見られるのだから(しかも勝者に代わってやるものなのに、結びが引き分けになっても今では行う)、ありがたみという点は確かに薄らいでいる。 とはいえ掉尾を飾る弓取式の勇壮さを是非見ておきたいし、筆者にとっては、これがなければ相撲場の一日が終わった気になれない。
何の前触れもなしに出したこの漢詩、袁枚の五言律詩「嘲眼鏡」(*8)の前半を引いたものである。 この詩は老眼鏡の耐え難い違和感を愚痴ったもの。ちょっと無理のある引用ではあるが、大相撲を見るなら、テレビ画面という一層を隔てて見るよりは、できるならば相撲場に足を運んで自分の目で見たいもの、という意味を込めて引いてみた。 だが…筆者は生で大相撲を見たいという願いの他に、記録しておきたいというところから、常にカメラを構えている。 そうすると、何層を隔てているのか、と言われてしまうのである。おまけに近視+乱視でしっかり眼鏡をかけている。まるで説得力なし、失礼しました。 (*8)袁枚「嘲眼鏡」清朝中期(井波律子「中国名詩集」岩波書店所収、平成22年) ここまで、筆者が相撲場でいかに欲張りな(浅いだけ?)見方をしているかを長々と書いてきた。ことによると、幕下以下の「あすなろ探し」を期待された読者もあるかもしれないが、 年に数度あるかどうかという飛び石的な「観測」では、正直なところ分からないというほかはない。ここからは、最後まで横道に逸れて、元に戻らない。 そもそも、大相撲の興行とは、どんなものなのだろう。これを解析的に眺めたものとして、新田一郎氏の想定する「4つの層」がある。すなわち、
(参考)新田一郎「相撲の歴史」講談社(講談社学術文庫)、平成22年(原書:山川出版社、平成6年)。以下、新田氏の所説はすべて同書による。 新田氏はさらに進めて、「スポーツ」「武道」「技芸」のいずれとして捉えるか、ということに説き及ぶ。無論、どう捉えるかは見る人の好みに委ねられるもので、多種多様な捉え方を許すのが大相撲の多面性である。 本稿は「我流」を冠しているので、ここで択一ということになれば、筆者は技芸を選択するであろう。というより、ほかの2つは、大相撲という技芸が見せる1つの相であると思うからである。 一定の規則の中で勝敗を競い合うという意味において大相撲はスポーツたり得るが、スポーツとなると勝つことが至高善となり、その内容は問われることが少なく、さらに大相撲を彩る装飾性や様式性もが捨象されてしまいかねない。 よって筆者にとってはほとんど意味のないものであり、少なくとも好みには合わない。武道ということになると甚だ分かりにくいのだが、恐らく大相撲の場合は「相撲道」というものに置き換えることができるのだろう。 「相撲道」を「相撲大事典」(*9)で引く。 (*9)金指基(財団法人日本相撲協会監修)「相撲大事典 第三版」現代書館、平成23年(初版:平成14年)
相撲道がスポーツと相容れないものとされているように読めるのが面白いところで、武道として捉える者が勝敗にこだわることをいやしめるとする新田氏は、こう解説する。 「なぜなら、土俵の上にあらわれるのは、日常の修業の成果の一端にすぎず、そこで一片の勝利を求めるよりも、勝敗に関わりなく「自分の相撲」を取ることによって修業を一歩進めることが、「相撲道」の実践者のあるべき姿なのである」。 「自分の相撲」を取れるようにするには、自分の持っている技芸を高めるしかない、と考えれば、結局技芸の持つ1つの側面ということになってしまう。 もちろん、技芸を高めるのが修業なのである。修業とは肉体的にも精神的にも錬磨することである。そう思考をめぐらせれば、これによって人間性の錬磨につながるということが一概に否定されるべきものではないし、そのように捉えて実践することも当然可能であると考えられる。 さて、大相撲は大衆娯楽であるから、大衆の思うところを読んで自らの行く末を定めなければならない。 それはつまり、「大相撲とはこういうものである」ということを伝える努力をしなければならないということでもある。 そして、大相撲を見る側は、それを広く読み取りながら、「大相撲かくあるべし」を意見する。このやりとりにより、大衆が自らの娯楽として大相撲を守り育てていくことになるはずなのであるが、現実にはそうなっているとは言い難い。 興行側により発信され大衆側に達する情報は必ずしも多くなく、大衆側は複数の角度から見ることをしないで無茶を求め、思う通りにならぬとみるや見捨ててしまう、まるでフランケンシュタイン博士(*10)のような振る舞いをなしているように思えることさえある。 (*10)シェリー(小林章夫訳)「フランケンシュタイン」光文社(光文社古典新訳文庫)、平成22年。フランケンシュタインは俗に怪物といわれる人造人間の名ではなく、それを生み出した天才科学者の名。 最後の締めくくりは、これ。
これを書いた人と、これが載ったものとを示すと、驚かれる方も多いだろう。書いたのは、「相撲」編集長だった池田雅雄氏。 そして載ったのは、ライバル誌だった「大相撲」なのだ(*11)。筆者が民俗学について一切通じていないのと、相撲道が芸能より大きいものとして扱われていることとが、 筆者にとりその理解を限定的にさせる要因にはなるが、思うところに最も近い内容であると思う。相撲を見る人見られる人、愉楽を得る人与える人、それぞれに心すべきであろう。 (*11)「相撲通74氏が考える 大相撲をよくする方法」(「大相撲」昭和57年8月号所収、読売新聞社) (平成22年2月3日起稿、同19日脱稿)
|