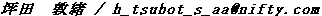| 言わんでもの記 9 |
| 谷風というのは、今さら言うまでもないが、古今を空しくするほどの大力士である。いろいろな意味で、大きな力士である。 まずは、その体格から。「大相撲人物大事典」(*1)の谷風梶之助の項に当たってみると、その体格は「188センチ 160キロ」とある。 現代であれば、ざらにいる。ところが当時この体格がいかに大きいものとして認識されていたかは、いくつかの随筆に「大男」として挙げられているという事実だけで窺うことができるだろう。 (*1)「相撲」編集部編「大相撲人物大事典」ベースボール・マガジン社、平成13年 そのまま「大男」という項で谷風を語る随筆が、「傍廂」(*2)である。その後篇巻之中には、こうある。 (*2)斎藤彦麻呂「傍廂」嘉永6年序(活字本:日本随筆大成編輯部編「日本随筆大成」第三期1、吉川弘文館、昭和51年)
著者の斎藤彦麻呂は明和5年(1768)三河岡崎の産、江戸に出たのは安永9年(1780)という。たいていこの類の大男伝説には大関釈迦ヶ嶽も登場するものだが、 釈迦ヶ嶽は安永4年歿なので、斎藤彦麻呂の目には触れていないし、見る機会を得たとしても覚えているかどうかギリギリの線といえようか。 今でいう中学生くらいの頃に初めて見た大男として、谷風の印象は絶大だったであろう。ここに記されている身長体重をメートル法で記せば、 身長は191cm、体重は169kgとなる。 もう一つ、「続飛鳥川」(*3)を紹介しよう。著者は分からないが、寛延から文化に至る江戸の名物を簡単に記したものである。 (*3)「続飛鳥川」文政年中か(活字本:国書刊行会(朝倉夢声か)編「新燕石十種」第一、国書刊行会、明治45年)
鬼勝は享保の力士とされているが、一般には寛永年中にいた身長245cmの超大型力士とされており、また元禄頃の力士とする書もある。 そして超大型力士として逸することのできない釈迦ヶ嶽もここに出てくる。この両者に並んで登場するということは、谷風が当時を代表する大男であったということを裏書きするものであろう。 この谷風たちを使って、こんな換算(?)を試みた人がいた。
これは弘化3年(1846)に奈良奉行として赴任した川路聖謨が、江戸の留守宅に残した養母に手紙代わりに送っていた日記「寧府紀事」の一節で、弘化4年5月15日のもの(*4)である。 勉強家の川路聖謨は、資治通鑑の晋紀を読んでいた。東晋の太興2年(319)に晋王を自称した南陽王の司馬保が、肥りに肥って体重なんと800斤になったというのが巻九十一(晋紀十三)に出ているとかで(実際に和刻本(山名本)に拠って眺めれば「保体肥大、重八百斤、喜睡、好読書、而暗弱無断、故及於難」とある。なお割註は略した)、 日本が誇る大男との比較を試みたというのである。谷風は代表に選ばれるの栄に浴したのであるが、計算したところ司馬保は谷風の3倍(!)というわけで、川路聖謨は結局「そんなバカな」と言っているのである。 川路聖謨は他の例も引いて「正史といえどもあてにはならぬ」とて嘆いているのだが、この計算には致命的な欠陥があったのだ。川路聖謨が用いた「1斤が160匁」(メートル法に直すと600gになる)というのは、あくまで川路聖謨自身が生きた時代に川路聖謨自身が生きた場所で用いられた量である。 この計算に従えば、司馬保は480kgとなり、大関小錦を2人連れてこないと勝ち目がないのだが、では東晋時代の800斤とはいかほどか。実は176kgで、いい勝負なのであった(ちなみに資治通鑑が成立(元豊7年(1084))した北宋での800斤は506kgであるが…)。 (*4)川路聖謨「寧府紀事」弘化4年5月15日条(活字本:大塚武松・藤井甚太郎編「川路聖謨文書 二」日本史籍協会、昭和7年(復刻本:東京大学出版会、昭和42年)) (参考)司馬光「資治通鑑」元豊7年(北宋)(訓点本:三島中洲校閲、山名善譲訓点「資治通鑑」鳳文館、明治15年(影印本:長澤規矩也解題「和刻本 資治通鑑(二)」汲古書院、昭和48年)) ここまでは体の大きさを中心にみてきたが、大力士として後世に伝わったのは当然ながら相撲が強かったればこそ。 その取り口については稿を改めることにして、谷風がいかに幅を利かせたかを、少しばかりみてみよう。つまり、存在感の大きさ。まずは端的なものから。
これは京都の色街を紹介した洒落本「六丁一里」(*5)の一節。刊年は天明2年(1782)、江戸で谷風が小野川に転がされて大騒ぎになった年である。 相撲「州」というのは、西川如見「華夷通商考」を真似てつくった作品だから。大相撲が始まればとかく雨が降り、 その悪天に引っ掛けて谷「風」が吹き荒れるというのは、なかなか巧みだ。 (*5)高慢先生「六丁一里」天明2年(活字本:洒落本大成編集委員会編「洒落本大成」第十二巻、中央公論社、昭和56年) 風の次は、風邪。
谷風と呼ばれた流行り風邪があったということは、割と有名ではあろう。この記述は「天明紀聞」(*6)にある。著者も成立時期も分からないものではあるが、天明年中のできごとを書き留めたものである。 この一件、天明元年11月のことという。谷風は流感で亡くなったが、その流感を谷風と呼んだとするものが多くある。 それがこの年の風邪ならば、世に言う谷風の63連勝は目減りして59連勝どまりになるはずだ。谷風が亡くなったのは寛政7年(1795)、そのときの風邪は御猪狩風と称される。 近年再三にわたって訂正されていると思うが、念のため。 (*6)「天明紀聞」(活字本:三田村鳶魚校訂「未刊随筆百種」第四、米山堂、昭和2年)
「寐ものがたり」(*7)の一節である。俳人のエピソード集なので、その内容の中心が谷風よりも柏莚にあるのは当然のことといえる。 いつの話かがはっきりしないし、この書の成立が谷風の時代から半世紀以上を経過しているということもあるので、柏莚こと市川海老蔵が誰のことなのか確定しにくい。 3代目(明和9年(1772)〜安永4年(1776)。元の4代目団十郎。安永7年歿)だろうとは思うのだが、谷風が達ヶ関から改名したのは安永5年で、このとき3代目海老蔵は隠居の身、指導者・研究者として在ったという。 谷風は名高き人として紹介され、それを見たオランダ人もべた褒めだったという。とはいえ、「五躰」は見るからに備わっていそうだが、「五倫」はどうやって分かるの? (*7)鼠渓「寐ものがたり」安政3年序(活字本:森銑三・北川博邦編「続日本随筆大成」11、吉川弘文館、昭和56年) 天下一の力士谷風らと並べて自分を一流であると豪語したというのは、懐徳堂の4代目学主となった中井竹山である。
「続近世叢語」(*8)巻之八に載っている逸話で、中井竹山はこんなふうに豪語したのだ。豪商鴻池は自分の弟子で、力士谷風は家に出入りしている。 自分とこの2人は、なしていることはそれぞれだが、みな天下の一流だ、と。中井竹山率いる懐徳堂は上方における学問の聖地、 その全盛期は天明末年から寛政4年(1792)の大坂大火までとされ、まさに谷風の全盛期と一致しているのだった。 (*8)角田九華「続近世叢語」弘化2年(影印本:「近世文芸者伝記叢書」第9巻、ゆまに書房、昭和63年) その中井竹山は、なんと谷風と勝負したのだ。谷風は中井竹山の弟子のようになっていたから、学問で雌雄を決するなどということはない。中井竹山は谷風と力比べをやった。なんと無謀な…
同じ内容の記事が2つ。漢文のほうは再び「続近世叢語」の登場で、和文で書かれているのは「在阪漫録」(*9)の二巻からとった。 中井竹山は大柄で力自慢だったそうで、谷風と枕引きをやったのである。最初は普通の枕でやったようだが、ついには枕の大きさに切った柱で引き合ったという。 とはいえ中井竹山、分というものを弁えている。だから、引っ張られるのはやむを得ないと。でも取られはしないと言い切った。 引きずられること座敷を3周、谷風といえども遂に中井竹山を引き離すことができず、枕引きで谷風に勝ったと評判を取ったそうだ。 (*9)久須美祐雋「在阪漫録」安政6年以降(活字本:森銑三ほか編「随筆百花苑」第十四巻、中央公論社、昭和56年) とうとう谷風に黒星がついた。鬼神もたじろぐ谷風をたじろがせた話をもう1つ。
大井の川に橋を架けなかった江戸幕府の政策はよく知られたところ、橋はなくとも東海道、何が何でも越えねばならぬ。 そこで大した膂力の川渡しが大活躍するわけである(どうして舟を使わなかったのか、とも思うが)。台に乗せて人を運ぶ場合もあったが、有名なのは肩車だろう。 天下の大男として自他ともに許す谷風も、難なく運び去られてしまったのである。川渡しのコメントは「こともなげ」という言葉がぴったりくるだろう。 人間は生き物だから乗せやすいのだそうな。とはいっても骨法があるのだろう。「息を吐いたときに上げろ」とは吊りの極意、それに似たようなものでもあるのだろうか。 この話、「退閑雑記」(*10)前編巻之十二に載る。谷風から直接聞いたという人から聞いたというのが松平定信の弁。 (*10)松平定信「退閑雑記」寛政12年(活字本:森銑三・北川博邦編「続日本随筆大成」6、吉川弘文館、昭和55年) 「相撲も第一」の谷風、だからこそ横綱の免許を与えられたのだが、免許を発行する吉田追風にもまた敗れ去ったのである。
吉田追風の「口頭試問」に、さしもの谷風もぐうの音も出なかったらしい。追風がどんな手を聞いたのかは知らないけれど、 ことによると谷風にとっては必要のない反り手あたりを聞いたのかもしれない。であれば、追風のセンスのなさが逆に恥ずかしいということになるとも思うが、 その場でやり込められた大力士谷風は、ちっちゃくなってしまったのであった。 (*11)高山彦九郎「江戸日記」寛政元年12月12日条(活字本:萩原進・千々和実編「高山彦九郎全集」第三巻、高山彦九郎遺稿刊行会、昭和28年) 偉大なる名力士谷風、その迷々伝は、あと1回。著名人ゆえ、笑いの種にもなるのだ。 (平成23年4月8日起稿、同17日脱稿、7月31日補訂)
|