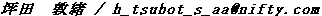| 言わんでもの記 23 |
| 平成25年5月場所、島根県出身の隠岐の海が新小結となった。島根県というと出雲国、古くは相撲どころとして名の通ったところだが、
昭和時代にはただの一人も新入幕力士を出さなかったのだ。隠岐の海の4人前の新入幕力士は、12代横綱陣幕久五郎になってしまうのだから驚くばかり。
さて島根県出身の新三役はというと、明治25年6月新小結の谷ノ音喜市以来121年ぶり、これは随分と話題になった。
谷ノ音の最後の三役は39年1月なので、それでも100年を超えている。そんな一世紀も前の力士、三役通算10場所を数える谷ノ音とは、どんな力士か? 引退までをごく簡単に記せば、このようになる。谷ノ音は慶応3年(1867)8月1日、今の島根県松江市東出雲町の生まれ、本名を深田久市という。明治16年、大阪相撲の朝日山部屋から初土俵、序二段まで取り進んだあと、 東京の雷部屋に転じて20年1月幕下二段目で登場し、23年1月の入幕、上記の通り25年6月新小結、27年5月新関脇となり、 手取り力士として活躍、41年1月限りで引退して年寄高島となった。 (参考)「相撲」編集部編「大相撲人物大事典」ベースボール・マガジン社、平成13年 (参考)小池謙一「年寄名跡の代々18 高島代々の巻」(「相撲」平成3年2月号、ベースボール・マガジン社所収) 谷ノ音は明治の名物力士であった。朝日新聞の記者だった栗島狭衣が伝える谷ノ音の名物ぶりである(*1)。 (*1)栗島狭衣「回向院から国技館へ =土俵の表裏今昔物語=」(「アサヒ・スポーツ臨時増刊」昭和15年春場所展望号、朝日新聞社所収)。栗島狭衣略歴については、門脇利明「「角力記」39人の相撲記者列伝④」(「相撲」平成18年9月号、ベースボール・マガジン社所収)参照
端折った部分は、朝汐を破った堂々たる一番と、伝家の宝刀も常陸山には通じなかった話なので、削るには惜しい。 だが些か長文でもあるし、(最高位に誤りがあるとはいえ)引用部分で彼の面目は充分に示されていよう。そう、彼こそは河津掛けの大名人、 百番が百番やったわけでもなかろうが、河津掛けと言えば谷ノ音、谷ノ音と言えば河津掛けなのだ。陸奥嵐にもそんな感じがあったろうが、その比ではなかったのだろう。 そんな相撲振りだからか、それとも物言い相撲での欲のなさゆえか、谷ノ音の幕内戦績は97勝92敗49分46預で、筆者自身で調べたことはないが預の数が古今独歩だともいわれる。 勝・敗・(分+預)でほぼ綺麗に三分されるというのも、珍しいのではなかろうか。 上司小剣の「相撲新書」(*2)には「重なる力士の伝」として14力士の略伝が載せられていて、谷ノ音は末席ながら堂々掲載の栄に浴している。 浴してといえば、「鳳凰、海山とも並び称された酒豪でもあつた」(*3)というから、酒は浴びるほど飲んでいたのだろう。 海山の酒豪ぶりが有名になりすぎ、谷ノ音は蔭に隠れてしまったものか、意外にエピソードが見つからないのだが、こんなのがある(*4)。 (*2)上司子介(小剣)「相撲新書」博文館、明治32年(復刻:ベースボール・マガジン社、昭和60年) (*3)石原漣「相撲"わしが国さ" 兵庫県・三重県・奈良県・和歌山県・島根県・鳥取県」(「野球界」昭和14年5月特輯号、野球界社所収) (*4)泉鏡花「入子話」(吉田昌志編「鏡花随筆集」岩波書店(岩波文庫)所収、平成25年(初出:「東京朝日新聞」大正11年10月7〜12日付))
柳川春葉・小栗風葉ともに、泉鏡花と並んで尾崎紅葉の門下。横寺町は尾崎紅葉の家で、鏡花は住み込みだった。紅葉と鏡花は大の右党で、 春葉と風葉は左党だったのだ。鏡花はこのおはぎを7つも食べている。ここに出てくる谷ノ音や剣山は名うての酒豪、 そんな酒豪とがっぷりに渡り合う柳川風葉の豪酒ぶりも際立つ。 要するに谷ノ音は、のんべでのんきな名力士だった。一方、のんべという話は聞かないが、のんきだという噂が聞こえてくる新小結の隠岐の海、 全然星が伸びず、中日に大関鶴竜と大激戦を演ずるも、結局敗れて1勝7敗、向こう給金崖っぷちの姿を目にして、 筆者は国技館をあとにした。隠岐の海は1場所で三役を明け渡したが、早く谷ノ音の最高位・関脇に追いついてもらわねば、と思うところである。 それから半月、筆者はいわゆる「積読(つんどく)」状態になっている未読の山から、1冊の本をつまんで眺めていた。 森まゆみ「鴎外の坂」(*5)である。鴎外の住むとこ住むとこ坂があった。坂を辿って鴎外の生涯を辿った評伝である。 (*5)森まゆみ「鴎外の坂」中央公論新社(中公文庫)、平成24年(原書:新潮社、平成9年) 明治25年、鴎外は当時の本郷区駒込千駄木町21番地の宅地を買って新居を建て、越した。旧居は同町57番地なので、距離はたったの300mである。 そこは団子坂の上、新居は観潮楼と称した。遥かに品川沖の白帆まで望めるからで、団子坂は正式には潮見坂という名だそうだ。 もともとここに建っていた家については、鴎外「細木香以」に出ているというが、筆者は未読である。細木香以は幕末の大通人で、 いわゆる「タニマチ」でもあったが、贅が過ぎて家産を蕩尽したという(ちなみに、細木香以の姪の夫の妹の息子は、芥川龍之介である)。その墓は、文京区向丘の願行寺にある。 その願行寺は、鴎外「寿阿弥の手紙」(*6)にも出てくる。願行寺には、江戸幕府御用達の大菓子商であった金沢丹後こと増田家の墓があるのだという。 「寿阿弥」と「金沢丹後」との関係を知るには、寿阿弥とは何?ということを書かねばならないので、さしあたって、この人名注(*7)を引く。 (参考)森鴎外「細木香以」(「山房札記」春陽堂所収、大正8年(初出:「東京日日新聞」「大阪毎日新聞」大正6年9月19日〜10月13日付)) (*6)森鴎外「寿阿弥の手紙」(「山房札記」春陽堂所収、大正8年(初出:「東京日日新聞」「大阪毎日新聞」大正5年5月21日〜6月24日付))。本文を引用するに当たっては、「鴎外歴史文学集 第四巻」(岩波書店、平成13年)所収の本文(小泉浩一郎注釈)により、章節を(*6・二)のように示す (*7)「鴎外歴史文学集 第五巻」所収「人名注」岩波書店、平成12年
寿阿弥は神田の菓子商「真志屋」の主人だったのである。のちに真志屋は没落し、最終的に金沢丹後に合流することとなってしまった。 いったん「鴎外の坂」に戻る。「『寿阿弥の手紙』も面白い小説である」(*5)としてその梗概を説いていく中で、 寿阿弥の墓に関連して「藤井紋太夫と力士谷の音もかつて寿阿弥の墓域内に葬られていたことを聞く」(*5)とあるものだから、筆者は大いに面喰らった。 現在、この墓は小石川伝通院にある。あと半月早く知っていれば、見に行ったものを… このとき、筆者は「寿阿弥の手紙」も読んだことがなかった。ちょっと落ち着いて、少しずつ調べてみたのだが、どうもおかしいのである。 「寿阿弥の手紙」の新聞連載は大正5年のことで、鴎外が探墓に行ったのは連載開始直後の5月27日(「二十七日(土)、雨。昌林院を訪ふ」(*8))であった。 谷ノ音の歿は大正10年7月16日なのだから、在世中である。ここまで「谷ノ音」といえば「河津掛けの谷ノ音」を指してきたが、 念のため、他の谷ノ音はどうなのかと思って「しこ名の代々」(*9)を当たってみたものの、該当しそうな者はいない。これは困った。 (参考)小泉浩一郎「解題(寿阿弥の手紙)」(「鴎外歴史文学集 第四巻」岩波書店所収、平成13年) (*8)森鴎外「大正五年日記」(「鴎外全集 第三十五巻」岩波書店所収、昭和50年) (*9)西尾義三郎「しこ名の代々 第8回 谷の音」(「大相撲」昭和58年5月号、読売新聞社所収) まずは「寿阿弥の手紙」を読んでみることにした。そも、鴎外が寿阿弥に注目したきっかけといえば、 鴎外が最初に著した史伝「渋江抽斎」執筆の際に出くわしたからだ。劇通抽斎の師に数えられる者の一人として、寿阿弥がいた。 「抽斎の師たり、年長の友たるべき人々」(*10・十三)は、「渋江抽斎」の「その十二」から「その二十四」に至るまで順次紹介され、寿阿弥については「その二十一」から「その二十三」にかけて記されている。 「私などの一読者からみた時、右の主人公(引用者註:渋江抽斎夫妻のこと)を取り捲く諸群像ともいうべき脇役の登場人物の方にも、 より心ひかれるものがあるのも事実である。第一には森枳園であり、寿阿弥であり、石塚豊芥子である」(*11)という中野三敏氏の言は、 何も読者に限ったことではなく、鴎外自身に最もよく当て嵌まる。最終的に「寿阿弥の手紙」が今のような姿をとるに至った経緯は、 例えば「鴎外歴史文学集 第四巻」に収まる小泉浩一郎氏の解題(*12)により知ることができるし、鴎外自身の作品にもその痕跡をとどめる。 鴎外が寿阿弥の手紙を入手したことは、「渋江抽斎」に「わたくしは大正四年の十二月に、五郎作の長文の手紙が売に出たと聞いて、 大晦日に築地の弘文堂へ買いに往った」(*10・二十二)とあることで知れるし、日記(大正4年12月31日)にある「吉川弘文館に往きて書を買ふ」(*13)もこれを指すと思われる。 鴎外の眼鏡には「此手紙の印刷に附する価値あるものたるを信ずる」(*6・二)と映ったが、なにしろ「文政頃の手紙の文」(*6・三)なので「今の人には読み易くは無い」(*6・三)として、 「全文を載せる代りに筋書を作つて出すことにした」(*6・三)のである。そして手紙を読み進め、読了はしたものの、 「寿阿弥の生涯は多く暗黒の中にある」(*6・十)とし、「何となく心に慊ぬ節があ」(*6・十三)ると感じ、 人を訪ね墓を訪ね、こうして成ったのが「寿阿弥の手紙」であった。 (*10)森鴎外「渋江抽斎」(初出:「東京日日新聞」大正5年1月13日〜5月20日付及び「大阪毎日新聞」大正5年1月13日〜5月17日付)。本文を引用するに当たっては、岩波文庫(岩波書店、平成11年改版)所収の本文(中野三敏注)により、章節を(*10・十三)のように示す (*11)中野三敏「解説」(森鴎外「渋江抽斎」岩波書店(岩波文庫)所収、平成11年改版) (*12)小泉浩一郎「解題(寿阿弥の手紙)」(同上) (*13)森鴎外「大正四年日記」(「鴎外全集 第三十五巻」岩波書店所収、昭和50年) (参考)鴎外が入手した手紙は鴎外により「寿阿弥手柬」と題され、その翻刻が「鴎外歴史文学集 第四巻」(岩波書店、平成13年)に収まる 「寿阿弥の手紙」のあらすじは、おおよそ以下のようである。
寿阿弥その人に興味を持って始めた調査は、遂に真志屋の代々をも考証するに至った。ここにその代々を記すこととする。なお13代以降を略す。 (参考)「鴎外歴史文学集 第四巻」(岩波書店、平成13年)に「真志屋始祖西村氏系図」としてまとめられており至便
浅井平八郎が「真志屋の祖先の遺物や文書」(*6・十七)を持ってきたので、寿阿弥研究は転じて真志屋研究となった。 その文書を鴎外は「真志屋文書」と名づけ(*6・十八)、この文書により展開したのが上の代々ということになる。 にわかに(原本)(別本)が登場して頭を悩ませるが、要するに過去帳が「余り手入のしてない原本と、手入のしてある他の一本と」(*6・二十四)の2種あるのだ。「前者を原本と名づけ、後者を別本と名づけ」(*6・二十四)たのも鴎外である。 「今遽に孰れを是なりとも定め難いが、要するに九代十代の間に不明な処がある」(*6・二十一)のは一目瞭然で、改竄と称しても良いくらいである。 別本では10代が9代より先に歿し、極めて不自然な姿となっている。詳細は省くが、寿阿弥と9代とは従兄弟同士に当たるものと鴎外は過去帳の記載により推測したので、 ことによると寿阿弥が真志屋11代となることを正当化するために10代を別人にしたのではないか、などと筆者は想像を逞しくするのだが、無論何の根拠もない。 ましてや、今では真志屋文書さえ存否不明で、再検討すら叶わぬ状態のようである。それにしてもだ。9代が実際に文化3年に歿したのだとすれば、 この改竄で10年も早く死に追いやられたことになるのだから恐ろしい。 (平成25年8月19日起稿、10月9日脱稿)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||