(京都市中京区) |
真ん中を占める池は法成就池といい、この池が「御池通り」の名の由来である。そもそも常に清泉が湧くから「神泉苑」なのだ。 北門から池に沿って南に歩くと、右に現れるのが本殿で、左には丹塗りの橋「法成橋(ほうじょうばし)」がある。橋を越えて、池の真ん中には「善女龍王社」。 善女龍王は、天長元年(824)の旱のときに弘法大師空海が勧請したという。願いごとを持って橋を渡り、善女龍王に願えば叶うのだという。 ただし、法成橋わきの看板には「願いはただ一つ」としっかり書いてある。善女龍王はインドの神、だからということか、御池通り側の門は、大鳥居だ。 数ある京都の祭の中で、第一に指を屈するものといえば、やはり祇園祭だろう。八坂神社の社伝では、貞観11年(869)に京で悪疫が流行したほか、 国内で地震などの災難が相次いだことから、6月7日に日本66か国になぞらえて66本の矛を立て、午頭天王を祀って14日に神泉苑に送ったという「祇園御霊会」を祇園祭の起源としている。 御霊会というのは、要するに疫病や天災を齎す怨霊を鎮める祭であり、祇園祭はその代表ということになる。神泉苑では、祇園御霊会の少し前、 貞観5年(863)5月20日に朝廷による御霊会が行われているが、これは疫病の流行が無実の罪を着せられて亡くなった者の怨魂によるものとの考えから、 崇道天皇(早良親王)・伊予親王・藤原吉子(伊予親王母)・観察使(藤原仲成?)・橘逸勢・文室宮田麻呂の怨霊を慰めたものだった。この御霊会は畿内から全国に広がり、 経を説くのみならず、相撲など諸芸が行われた。 相撲と神泉苑といえば、相撲節。弘仁12年(821)奏上の「内裏式」によれば、相撲節は7月7・8日の2日間で、7日は神泉苑、8日は紫宸殿を会場とした。 古いところでは大同2年(807)から神泉苑での相撲節の記録がある。この年は儀式の改編があり、服属儀礼としての形が整えられたと考えられている。 その後、7月7日の節日が7月16日に変わり、さらに7月下旬にずれていくとともに、娯楽行事に変貌していったようで、神泉苑での相撲節は承和3年(836)を最後に記録がなくなった。 貞観年中(859~877)の「儀式」になると、会場は「便処」になってしまうのだ。大極殿のような枢要の施設でのみ用いられる緑釉瓦が、神泉苑からも見つかっているという。 神泉苑がいかに重要であったかを示すとともに、相撲節のステータスの推移をも示しているように思う。 |
|||||
| (参考資料) | |
| ・ | 「神泉苑」 |
| ・ | 「内裏式」 |
| ・ | 「儀式」 |
| ・ | 「日本後紀」 |
| ・ | 「続日本後紀」 |
| ・ | 「日本三代実録」 |
| ・ | 「類聚国史」 |
| ・ | 「祇園本縁雑実記」 |
| ・ | 林屋辰三郎「京都」 |
| ・ | 髙橋昌明「京都〈千年の都〉の歴史」 |
| ・ | 坂上康俊「日本の歴史05 律令国家の転換と「日本」」 |
| ・ | 大日方克己「古代国家と年中行事」 |
| ・ | 新田一郎「相撲の歴史」 |
| ・ | 八木透「祇園祭-その創始と変遷」(京都市文化市民局文化財保護課(監修)「祇園祭創始一一五〇年記念 祇園祭 温故知新 神輿と山鉾を支える人と技」所収) |
| ・ | 竹森章「京都・滋賀の相撲 まつりと力士の墓」 |
前画面に戻る 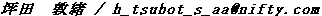 | |




