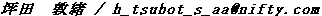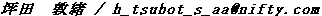横綱(五)
谷 風・小 野 川 横 綱 免 許
(前項※1)によれば、年寄連から寺社奉行に、「相撲故実の家である細川家家来吉田追風から、
谷風・小野川を門弟に加え、相撲場を検分(見物とあるが、検分のこと)した上で、横綱を伝授したいという申し出があり、
これが叶うならば、我々相撲を生業とする者にとっては、渡世の助けとなるであろうから、是非認めていただきたい」という願書が提出された。
併せて、細川家からも寺社奉行へ、「行司の要望により吉田善左衛門を相撲場の検分に遣わしたい」という伺いを立てている。
但し、追風自ら土俵場に臨んでの横綱伝授という願いは叶わなかったが、横綱免許自体と、それを本土俵の上で披露することは認められ、
寛政元年(1789)11月28日、冬場所 6日目の土俵に於いて触れがあり、翌日に披露及び土俵入りが行われた((前項※1)に「角力六日目に土俵にて相触れ翌七日目より谷風、小野川、右横綱を結び一人土俵入りいたし候」とあるので、
6日目に横綱伝授が行われ、 7日目に土俵入りが披露されたという説もある)。
なおそれより早く同月19日、免許授与が司家私邸で行われ、谷風には横綱免許状と故実門人証状、小野川には故実門人証状のみが手渡された。
小野川の横綱免許状は遅れて12月(14日?)に与えられたようだ。説明に拠れば、はじめ司家は、谷風のみの横綱免許を考えていたが、
有馬家(小野川を抱える主家)からの申し入れ(横鑓?)で、(しぶしぶながらと想像されるが)小野川への横綱免許を決めたため、その手続きに時間を要したのだろう、とのことである。
酒井忠正氏は「五條家目代の追風が、五條家に対して小野川追加の了解を取りつけるために時間を要した」と説明しているが、
能見正比古氏は「五條家と吉田家との対立を考えると納得できない」としている。
一方、新田一郎氏曰く「吉田家(※1)が、行司としての識見を買われてであろう、江戸初期に京坂での相撲興行に関与していたこと、
及び遅くとも元禄ごろには細川家に抱えられたことは確認できるが、五條家(※2)が「相撲の家」を名乗ったのは、相撲興行が軌道に乗ってから後のことであり、
それに先んじて相撲故実を伝えていたのではない」と。これによると、能見氏の言う「五條家と吉田家との対立」も何も、五條家が同じ土俵に立っていないということになってしまう。
これにより長く不入りが続いた相撲興行は一気に黄金時代に突入した。
(※1)吉田家が寛政元年に幕府に提出した「祖先書」(「相撲隠雲解」や「相撲式」にもあり)や「由来書」は、
手っ取り早く言えば、「相撲の家元」として吉田家を強烈に天ヶ下に知らしめるための創作である。
途方もない捏造であるが、これを咎めてはならない。大名・武家・豊かな町人をはじめ、家系を尊ぶ風習が盛んで、それゆえ「相撲の司」の地歩を築かんためには、
まずは系図を飾り立て、遥か遠くの先祖を誇った。従って当然史実には存在しない。因みに横綱常陸山の編んだところの「相撲大鑑」でも、一応遠慮して「これ社寺の縁起とひとしく、実は信拠すべきものなるや否や、決し易からず」と記しているが、
言いたいことは「信用できる筈がない」である。常陸山は横綱免許を受けた者、従って司家の故実門人である。流石豪放横綱常陸山、思い切ったことを言うものである。
(※2)江戸前期に公家の家業を列べた「諸家々業」によれば、五條家は「儒家紀伝道」の家の一としてあり、
文化年間に追補された同書の「付録」で「五條家を相撲之家之様に申候」として、野見宿禰の後裔であるがゆえにいつしか斯く言われるようになった、と書かれているのが五條家と相撲との関わりに関する記述の古いところである。
五條家は力士に「絵符帳面(宿駅などでの便宜を保証する証明書)」を発することがあった。これは五條家が相撲について由緒ある家であるからだといわれるが、文政年間より前には確認されない。
とどのつまり、谷風・小野川の当時は五條家は「相撲の家」も何もあったものではない、ということになる。
なお、復刻「相撲講本」に、こんな記述がある。
−大正十四年に京都にて五條為功子爵に(花坂吉兵衛氏が・筆者註)拝謁した時此事(行司の家としての五條家・筆者註)について伺ひたるに左の如き御話であった。
「固より我家(五條家)の司家たるは世、人共に許す所であるが、惜しい哉一切の書類灰燼となり(当時御縁戚の菅家に寄寓して居られた)論より証拠をいふことが出来ぬが、
伝承によれば嘗て九州に阿蘇ヶ嶽なる力士あり「当時吉田氏は行司にして我が目代を務め居り」細川家より阿蘇ヶ嶽に対し九州一円の横綱免許を申請し来つたから、細川家に頼つた吉田氏に適宜の処置を委任したのが爾来例となつたさうである云々。−
こんな具合で「一切の書類灰燼となり」「伝承によれば」では、てんで参考にならない。なお、阿蘇ヶ嶽の関係に就いてはもうしばらく後に書くことになろう。
前ページへ 次ページへ
前画面に戻る