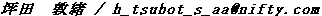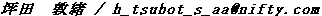横綱(二十四)
三段構えとせり上がりとの関係
三段構えの説明は前項に記した通りではあるが、「古例に則った」とされる三段構えが明治42年以前に行われたという記録が見当たらないのである。
新田一郎氏や小池謙一氏は、「旧国技館開館のときに初めて吉田司家によって持ち込まれたものではないか」と考えている。
新田氏はさらに、「相撲伝書」にある「手合いの上・中・下ほかの型(※1)」からヒントを得たのではないかという意見を持つ。
吉田司家の故実門人となっている彦山光三氏は「相撲道綜鑑」の中で、「はじめの三つ、すなはち上・中・下段の手合は、「三段構え」の基礎となつて、
現在では阿吽の玄理、虚実の妙趣を蔵する、相撲道の真諦とされてゐる」と記し、やはり立ち合いの上・中・下の形がモデルであるとしているから、「相撲伝書」ヒント説は図星かも知れない。
のちのちにより古い記録が出てくれば変わる事もあるかも知れぬが、やはり明治42年以前には「三段構え」なるものはなかったのではないか。
そう考えると、問題がまた一つ発生するのだ。現在横綱土俵入りの「せり上がり」は、三段構えを下段から上段へ向けて連続して行うものと説明されている(※2)。
しかし、二代目梅ヶ谷や常陸山、さらには小錦の映画を見れば分かるように、明治42年よりも前から「せり上がり」はちゃんと存在するのである。
(十七)項に引いた「相撲隠雲解」を見ると、「せり上がり」の記述は見当たらない。手拍子と足踏みしか書かれていない。
では、せり上がりはどこから入り込んだのか。これについては後にも記すが、今度は(二十二)項に掲載した丸上翁の不知火光右衛門実見記が生きてくる。
要するに「二字口で柏手を打ち、三足半で土俵中央に進み出て、柏手を打って四股を踏むまでは誰もが同じ、
そのあと、普通にやれば右手を前方に出して左肘を曲げて左手を胸につけて(直前の四股で腰をやや下ろした体勢から、次の四股に移るために)体を引き立てて両腕を左右に広げる(※3)だけであるが、
不知火の場合は、四股のあとになお腰を割って、右手を出すときは(漠然とではなく)前に滑らせるようにやった」ということである。
結句何を意味するかといえば、せり上がりはその不知火が発明した演出上の新機軸(香山磐根氏の説)、ということである。
さて、太刀山がやった「両手を広げた状態でせり上がる型」は、雲龍の型であるというのだが、雲龍は本当にいきなり両腕を広げてせり上がったのだろうか。
残念ながら証拠がなく、丸上老人の談話にもこれと言って大したことは出てこない。太刀山に教えた庄之助と、雲龍本人を冥土から呼び返して実演してもらう以外に方法はないようだ。
まあいずれにせよ、雲龍・不知火の頃から動作に折り目がついて現代の土俵入りに近づいたとする池田雅雄氏の所説によれば、
雲龍にもせり上がりがあっても不思議ではない。但し確証は得られない。
太刀山の型の話はこのぐらいにして、それではなぜに「せり上がり」と「三段構え」が結びついたのであろうか。
想像するしかないのだが、太刀山の型は別として、常陸山や梅ヶ谷のように、左手を脇腹につけて右手を右下に流す型からせり上がる場合は、
「三段構え」の型によく似るわけである。或いは、逆に「相撲伝書」の立ち合いの型にヒントを得、横綱土俵入りのせり上がりの型に似せて「三段構え」を発明したのかも知れない。
そんなところだろう。少なくとも栃木山の頃にはもう「せり上がり」と「三段構え」とが結びついていたらしい。
かといって、今更「三段構え」と「せり上がり」を無理に分離することもない。今や、横綱土俵入りは、柏手と四股踏みによる清めの儀式だけでなく、
確かに一種のショーではあるが、相撲の型をも端的に示すものとして位置づけられている、ということになっている。
「相撲の型」を最強者たる横綱が「模範」として土俵入りを行うことで天下に知らしめる、というのはいいことであろう。
せり上がりは「千鈞の巨岩をさし上げる気組みでやる」もの(※4)とされている。そのためには「三段構え」の形でせり上がっていくのが最も力感溢れて見映えが良かろう。
確かに両者の結びつきはただの附会であったのだろうが、こじつけとはいえ、いい説明だと思う。
その代わり、「せり上がり」が「三段構え」に由来する、というのが誤りであるということは、間違いあるまい。
(※1)「一 手合ひと云ふは相撲の初発に声を発し練り合ふ事なり。是れ即ち活気堅強の備を設く。手合ひに声を発する事、力は声に連れて出るの理也、手を揚げ四肢心体に強を発し勇気全体に充る時、
心体一同にして其業滞る所なし。縦ば戦場敵に会て声を掛け合ひ互に勇気を発するが如し、声なきとは勇気の起るたよりなし。猶又相撲とるべき已前砂を取て両掌に揉み込み筋力をたすけ出す両掌の砂を金剛砂といふ。力足を踏む事逆上の気を下に止めて両足に筋力を顕す。
是れ発強の勢ひ相撲古法の教なり。然るに近年手合ひなく、声も掛け合はず、力足も化粧に踏んで古法をもどく、是等勇気を発する事を弁へず全く相撲の勢ひにあらず。唯先に入り跳ねつくことのみひしと心懸て外を知らざるゆへ、跳ね突事のはづれたる時体理の業を尽す事あたはず、勝ても勝たる理を知らず負者も又然り。
諸行始あり、古法の格式ありたきものなり。手合ひよりはじめても先後の理は彼我の虚実にあり。先勝も始めのみにはあらず後の先とて敵の来り様あしき節は後の先にて破る事多し、故に上手は始終先を追つて勝ち下手は始終先に追はるゝものなり。其後進退動静の業に熟し、敵に己が非を見せざれば敵の入べき所なし、
呼吸乱れず気逆上せず心体勇気の収出を知る、古法の教にも常住座臥心に徹し忘れざれば自ら業熟す勝負は己にありて他にあらず」(「相撲伝書」)
「上段の手合 上段の手合は、両手の指、頭上にあり、これを立眼相と云、勝負の情を察するものなり。
甲冑の理合も、各心体の進退動静の所にしたがふ、相撲白心の業、甲冑を着して不自在といふにもあらず、心体業に熟するときは業これにしたがふ。
中段の手合 中段は、両手指、両眼の通りに揚る。
下段の手合 下段は、両手肩下にあり。
奇相の手合(或は無形の手合ともいふ) 奇は変動して常なく、敵の強弱虚実にしたがひ、円転発機の象あり、無形とは、かたちを見せず、是即象なきものは破べからずといふ義なり。
陰陽の手合 両手に高低あり。故に名とす。
居眼相 居眼相は手合なり。
相撲双方居合、行司団扇を入れ、声をかけざる以前、敵不意に来るを防ぐ形なり、跡へ衝返へされず、両脇へさし込まれず、帯をとられず、敵の眼相体理をうかゞひ、その来るべき所を察し、勝負の情を知るものなり、臨機応変にして進退を究む、手を膝にかたく乗する事、膝を堅くおさゆる事、よろしからず、手足体理ともに、進退動静出入自在なるを欲す」(同書)
(※2)「手合の型をとつて、相撲立合の根本精神と、気合の本質をあらはしたものが、三段がまへであり、三段がまへは、相撲人が二人、相対して行ふのが定法であるけれども、手数入りの際は、単独にやゝ形を変へて行ふのである」(彦山光三著「相撲道綜鑑」)
(※3)丸上翁の実見記のうち、「体を引立て両手を水平に左右へ延ばす」の件、まともに読めば「せり上がりながら両手を広げた」ということになろうが、加藤健治氏は「それは常陸山が手拍子を打って左右の手を左右に開いたのでセリ上がりとは違う」とバッサリ斬り捨ててしまった。
しかし同じ文章の中で加藤氏は「不知火光右衛門は非常に土俵入りが華麗だったそうで、両手を広げたさまが鶴の舞うようだ、と表現されている。となると、不知火も初めは片手をワキに当てて、セリ上がって最後に両手を広げた、ということになるのかも知れない」とも言っている。
確かに実見記を「体を引き立ててから右手を下ろさないまま左手を上げた」と読むこともできるし、そうであれば、せり上がりは現在のものと同じということになる。
動作としてはこちらの方が自然だと思うのだが、証拠立てることはできない。
(※4)彦山氏が昭和 9年夏に23世吉田追風を訪れてこう教わったという。「腰をすえ、紅さし指(薬指)のつかいかたに重きをおくことが秘伝の一つでござっす。
この指をもとにしておっつけなければ、おっつけることなんかできまっせん。下の構えの眼は、上目もふし目もいけない、まっすぐ十五間ぐらい前をみつめるのが本格とされております」。
前ページへ 次ページへ
前画面に戻る